🐥 はじめに
発達障害のある子どもを育てる毎日は、一般的な育児とは少し違う大変さがあります。
そして、その「大変さ」は成長とともに形を変えていくものだと、今になって思います。
ここでは、ADHDの長男とASD(自閉スペクトラム症)の次男を育ててきた中で感じた
ストレスの内容と強さの変化を、時期ごとに振り返ってみたいと思います。
🐥 乳児期:寝ない・泣く・抱っこばかりの毎日(ストレス90)
長男の赤ちゃん時代は、とにかく寝ませんでした。
おんぶ紐は嫌がり、日中はずっと抱っこ。
トイレに行くときは、ベビーベッドに寝かせてダッシュ。
その数十秒の間に号泣が始まり、慌てて戻る……そんな日々でした。
夜は添い乳でようやく寝てくれましたが、
「添い乳=ズボラ」という世間の声に罪悪感を抱えながら、
それでも眠るための手段として続けるしかありませんでした。
長男がようやく夜寝るようになった頃、次男が誕生。
……そして、また「寝ない赤ちゃん」再び。
ただ、次男は短時間ならバウンサーで過ごせたのが救い。
それでも母は常に寝不足で、日々フラフラでした。
🐥 次男乳児期:入退院を繰り返した1年(ストレス95)
次男が生まれて間もなく、私は職場復帰しました。
しかし、その年だけで6回の入院。
肺炎、ノロ、その他の感染症……毎回別の病気。
「免疫に問題があるのでは?」と検査してもらいましたが異常なし。
ただただ“運が悪かった”という結果に終わりました。
昼間は祖母が病院を見てくれて、私は夜だけ泊まり込み。
昼間は仕事、夜は病院。
ほとんど寝ずに過ごしたあの頃が、振り返ると一番つらかったかもしれません。
それでも当時はまだ若く、気力だけで乗り越えた気がします。
🐥 小学校・保育園期:別々の登校・支援と仕事の両立(ストレス80)
長男が小学校、次男が保育園に通い始めた頃も大変でした。
毎朝の支度・送り迎え・行事・先生とのやり取り……。
二人の特性がまったく違うため、支援内容もコミュニケーションもそれぞれに調整が必要。
それでも少しずつ、「母としての耐性」がついてきた時期でもあります。
「発達障害だから仕方ない」「できることをやればいい」
そう思えるようになったことで、ストレスの感じ方も変化していきました。
🐥 小学校高学年期:母のメンタルが鍛えられた頃(ストレス65)
長男が高学年になると、学校との関わりにも慣れてきて、
先生との連携もうまくいくようになってきました。
次男も支援級で安定して過ごせるようになり、
ようやく「少し楽になってきた」と感じられるように。
この頃から、
「頑張りすぎない」「頼れるものは頼る」
という自分なりのリズムを掴めてきたのかもしれません。
🐥 中学期:思春期で再びストレスの波(ストレス80)
長男が中学生になり、思春期の壁にぶつかります。
反抗期・自己否定・不登校ぎみ……。
「どう関わればいいのか」がわからなくなり、再びストレスが増大。
ただ、支援の先生や心理士さんとの面談を通じて、
「本人が自分で考える時間を持つことも大切」だと気づきました。
母がすべてを抱え込まなくてもいいんだと、少しずつ実感。
🐥 現在:高専生と中学生の母として(ストレス40)
今、長男は高専に通い、次男は中学1年生。
次男は支援級から通常級に移行しました。
学校に出向く機会はまだまだありますが、
以前のような“常時緊張状態”ではなくなりました。
長男も自分なりに生活を立て直し、
私はようやく「気が抜けた」と感じています。
今のストレス度は40くらい。
振り返ると、幼児期のあの大変さをもう一度やれと言われたら無理。
でも、あの頃があったから今がある。
少しずつ、母も子も成長していくものなんだと思います。
おわりに:ストレスは“減る”というより“変わる”
発達障害のある子を育てていると、
ストレスが「なくなる」日はなかなか来ません。
でも、確実に “変化していく” のを感じます。
昔は「全部自分がやらなきゃ」と思っていたけど、
今は「誰かと一緒に支えていけばいい」と思える。
少しずつ、肩の力を抜けるようになった今は、過去のがむしゃらだった私に言いたい、。
『楽を知らなかったから、頑張るしかなかったけど頑張れてよかった!!
徐々に(身体は)楽になるよ。歳と共に体力はなくなるけどメンタルは強くなるから、何とかなるからね』☺️💕
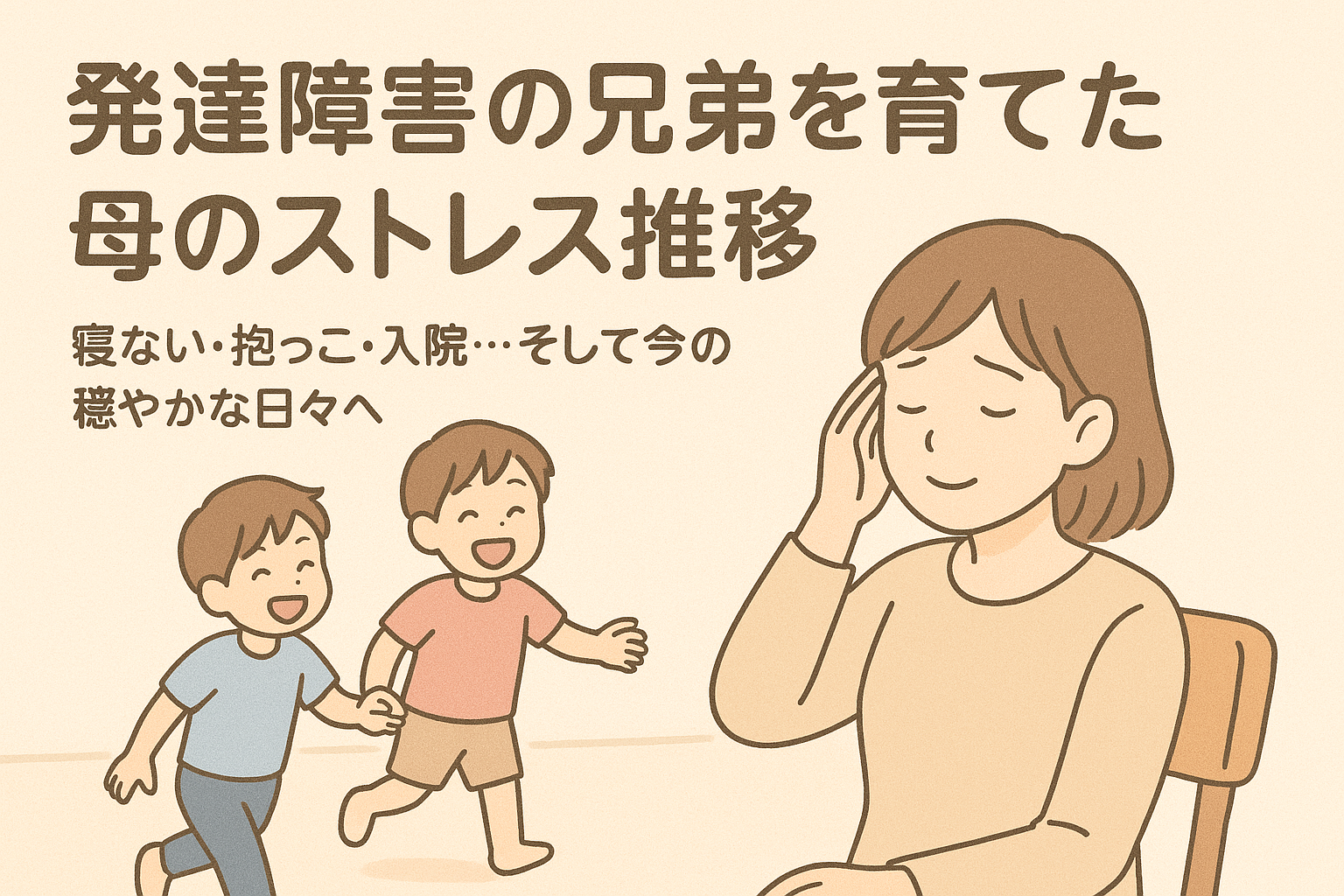
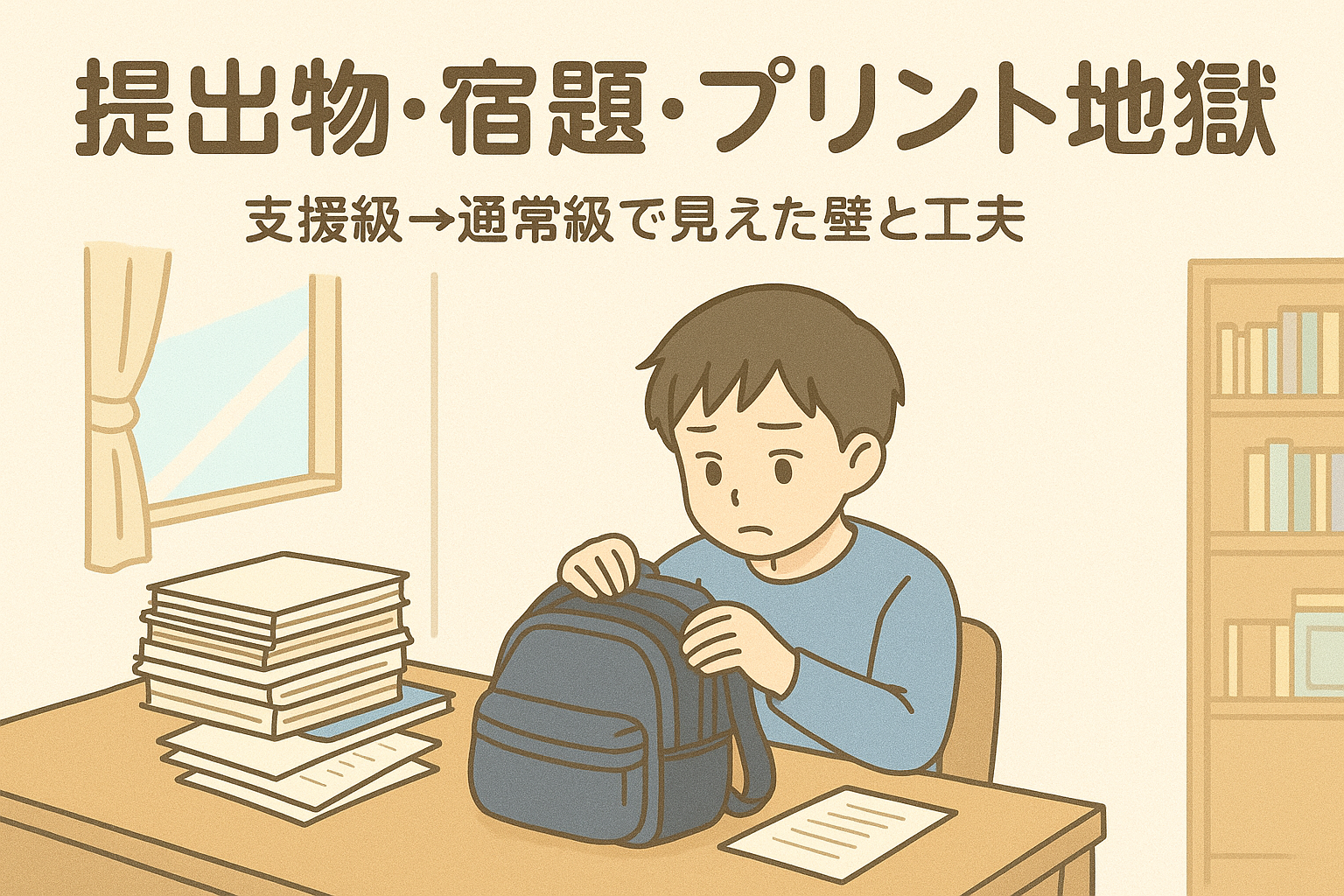
コメント