🍁 はじめに:支援級から通常級へ――「プリント地獄」の始まり
小学校時代、次男は支援級に通っていました。
教科書とノートさえあれば何とかなり、忘れ物をしても「貸してもらえる」「先生が助けてくれる」環境。
困ったときは支援の先生にすぐ助けを求められる、安心の場でした。
親の私は正直、毎日のサポートにそれなりに苦労はありましたが、次男本人はのびのびと過ごせていたと思います。
しかし中学に入学すると状況は一変。
IQテストの結果から知的クラスには入れず、通常級に進むことになりました。
「本当に大丈夫かな……」という不安の中でのスタートでしたが、意外にも次男は学校生活にすんなり馴染みました。
🍁 人間関係は“鈍感力”が味方に
次男は、人の顔を覚えるのが苦手で、何を言っているか分かりにくい話し方をします。
空気を読むのも苦手で、正直「クラスで浮かないかな」と心配していました。
けれど、男子中学生というのはまだまだ幼く、むしろ“天然キャラ”として受け入れられたようです。
一部ではからかいのようなこともあったようですが、次男は気づかずスルー。
本人が気にしないことで、嫌な雰囲気も続かずに済みました。
“鈍感力”が、まさかの最強バリアになってくれたのです。
ただし、問題は学習面。
ここからが本当の“地獄”の始まりでした。
🍁 教科ごとの本・提出物・プリントが山のように!
中学校は、教科ごとに本が多い!
ワーク、ノート、資料集、プリント、スケッチブック…。
「今日は何の授業があるか」を考えて荷物を揃えるのが大変です。
次男は、整理整頓が大の苦手。プリントはカバンの底でぐしゃぐしゃ、ワークは行方不明…。
最初の数週間は毎日バタバタでした。
工夫①:教科ごとにB4チャック袋で“まとめ持ち”
そこで私は、長男のときに使っていた中身が見えるアミアミのB4チャック袋を活用。
教科ごとに袋を分け、ワーク・ノート・資料を全部まとめて“ひと固まり”で管理する方式に。
「この袋を持っていけばその教科はOK」というシンプルなルールです。
次男は几帳面ではないけれど、「袋ごと持っていく」ならできる。
多少ぐちゃぐちゃでも、もうそれで合格です。
🍁 提出物管理は“母子連携プレー”で乗り切る
提出物の多さも中学校の壁。
英語はワーク、社会はノートとプリント、数学は問題集……テスト前にはそれぞれ提出物の締切が出されます。
でも次男は、黒板に書かれた指示をメモできません。
そこで、母は学校に確認し、毎回教科ごとの提出一覧(決まって提出になるワークなど)を作成して把握し、「丸い赤シール」を提出物に貼ることにしました。
チェックは本人に任せつつ、抜けているところや進みが遅いときだけフォロー。
「出せない」より「自分で進められる」を優先するようにしています。
テスト前も、勉強より提出物を終わらせることを優先。
提出物はそのままテスト範囲なので、結果的に学習の復習にもなります。
工夫②:忘れ物対策に“音声リマインダー+忘れ物バンド”
忘れ物対策として、次男は手首につける忘れ物バンドを使用。
さらにアレクサにも「体操服!」「ワーク!」など音声リマインダーを登録して、自分で声かけできるようにしました。
それでも忘れる日もあります。
そんな日は「まあ、仕方ない」で終わり。
完璧を求めないことが、我が家のルールです。
🍁 おわりに:支援が少なくても“できる仕組み”があれば大丈夫
支援級のころとは全く違う世界に飛び込んだ次男。
最初は「大丈夫?」と心配ばかりでしたが、今は“自分のやり方”で何とか乗り切っています。
支援が少ない環境でも、「できる仕組み」を整えれば、発達特性のある子でも自信を持って進めるかな、と思っています☺️もちろん『できる範囲で・・・』
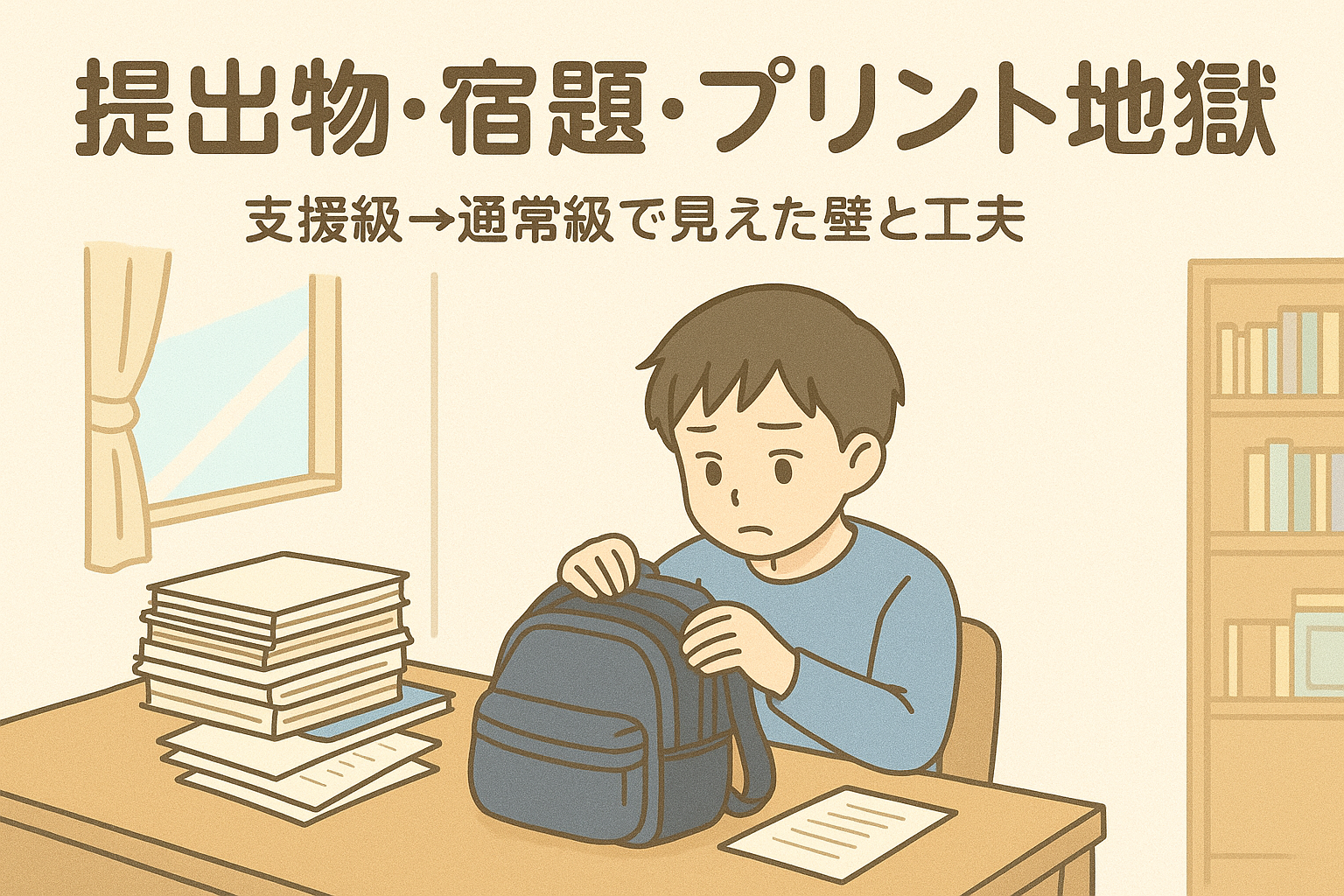
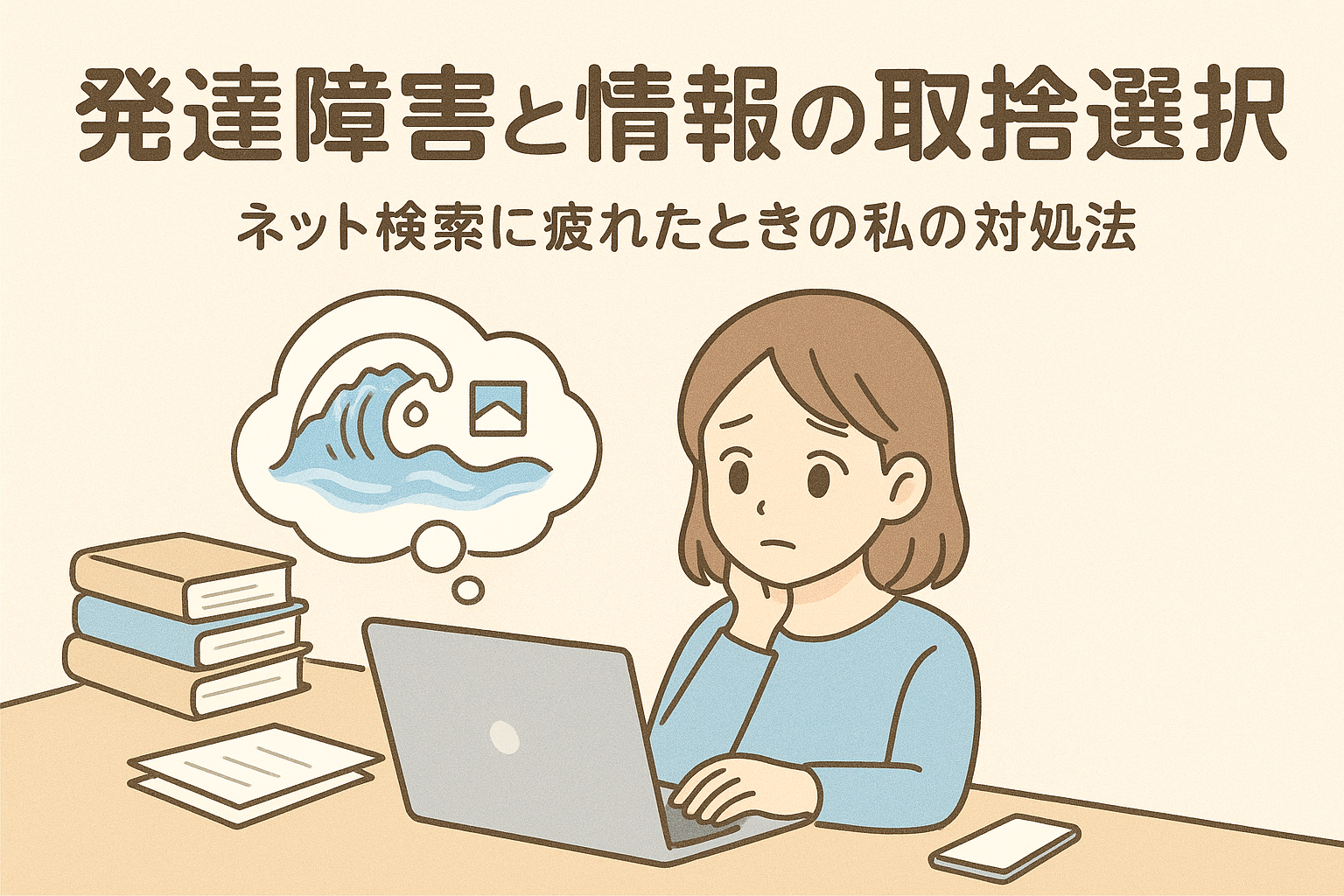
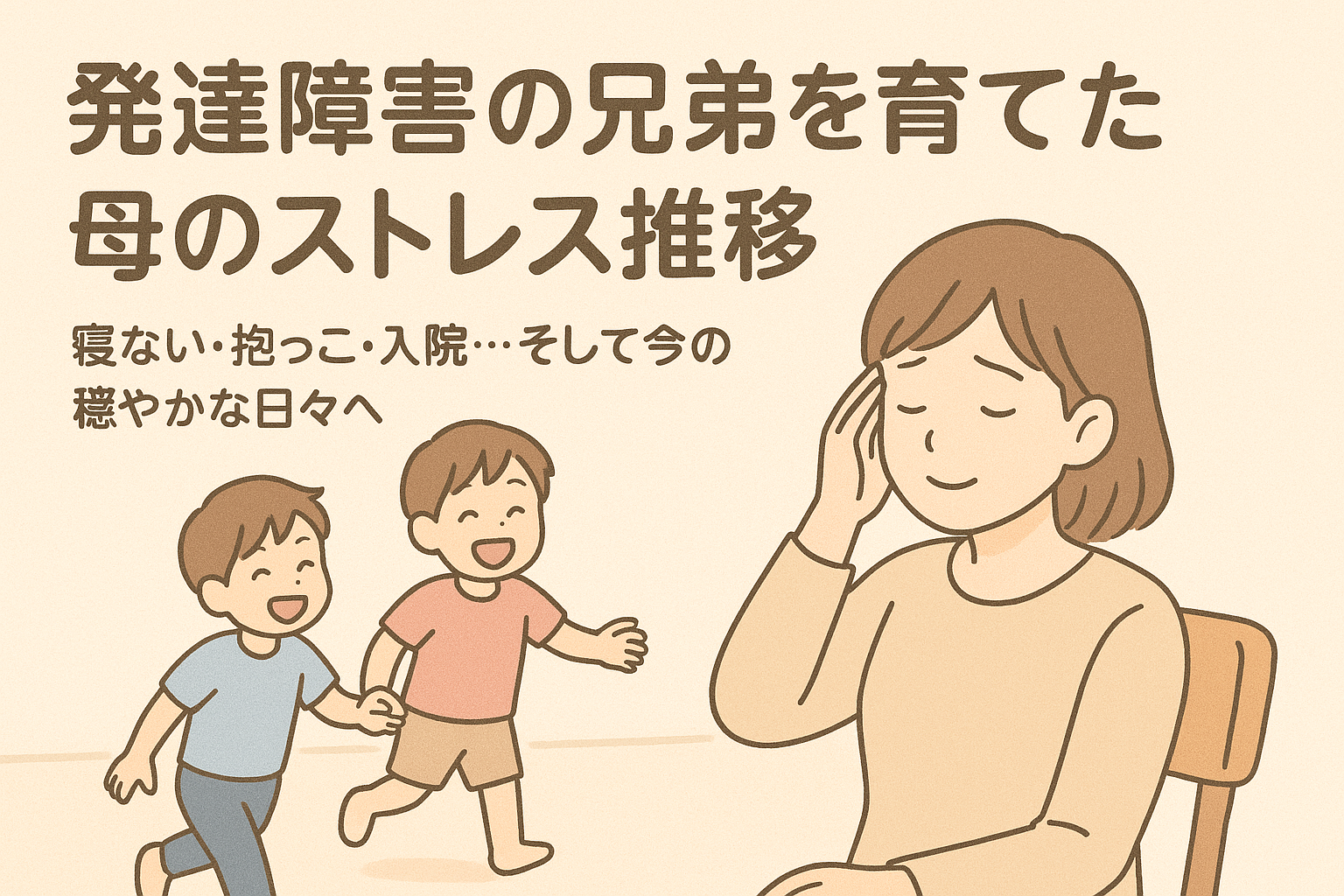
コメント