〜無気力から高専合格までのリアルな1年〜
🟠 中学での無気力生活と思春期
中学校に入ると、長男は一気に無気力になりました。
部活にも入らず、家にいるものの何もせず。夜更かしをして朝は起きられない。話しかけるとイライラして反発、無言、あるいは逃避。生活はどんどん乱れていきました。
遅刻は日常。宿題は出さず、授業にもついていけない。親としてできることが見えず、悩む日々が続きました。
今思えば、生活全体に困りごとが多かったため、何から何まで手伝ってしまい、「過介助」になっていたのかもしれません。
長男はそれを“口うるさい”と感じていたのでしょう。でも、自分で起きられず、時間通りに登校できない状況では、親の手助けなしに生活を回せなかったのです。
この生活が2年続きました。成績も目を覆いたくなるような状況でした。
🟠 志望校が決まっても、行動できない
中学2年の3月、長男が突然「高専に行きたい」と言い出しました。
きっかけは、1学年上の友達が高専に進学し、寮生活を始めたこと。
寮の写真や給食、授業の様子を毎日のように見せられ、「一緒に来ないか?」と誘われていたそうです。
高専について、私もこの時はよく知りませんでした。
調べてみると、高専(高等専門学校)は中学卒業後に入学できる5年一貫の専門学校で、工学や情報技術を高校1年生から本格的に学べる環境とのこと。
そして、卒業時には「準学士」の学位が得られ、就職率も非常に高い。
まさに長男にうってつけの学校だと感じました。唯一の得意科目である数学、そして好きなパソコン。興味が持てたら打ち込める――そんな子だからこそ、ここに導かれたような気がしました。
しかし、志望する高専の偏差値は62。長男の現在の実力は…模試未受験でしたが、50以下だろうとは感じていました。
「ここから希望はあるのかな?」「スイッチは入るのかな?」と、親としては不安しかありませんでした。
🟠 オープンスクールで見た「高専のリアル」
9月、高専のオープンスクールに家族で参加しました。
私はそこで、はっきりと「この学校に行かせたい」と思いました。
- 授業内容が専門的で面白い:プログラミングでロボットを動かす、動画やゲーム制作の実演など、興味を引くものばかり。
- 個性が尊重される校風:展示物にもアニメやゲームが使われていて、「オタク歓迎」という雰囲気が自然にあった。
- 制服なしで自由だけど、ルールは厳格:SNSやいじめに対する管理も行き届いていると聞き、安心感もありました。
ここなら、長男の個性が生きるかもしれない。そう強く感じました。
🟠 ギリギリで訪れた転機
とはいえ、すぐに長男が行動を起こすわけではありませんでした。
信頼していた塾の先生からは「高専より偏差値40の公立校のほうが合っているのでは」とのアドバイスも受け、長男はショックと受けていた様子でした。
塾の先生には『ダメでも良いので第一志望は高専にしますと伝えました』
塾の授業は減らし、志望校に向けての別の方法を模索しました。
そんなとき、夫が見つけたのが「高専専門のネット塾」でした。長男はそのサイトを見て、初めて自分から「このプランを契約してほしい」と言ってきました。
5教科の3年分の授業が、好きなところから視聴できる仕組み。しかも高専受験に特化している。
高額ではありましたが、長男のやる気を初めて感じられて、即決しました。
時はすでに11月。そこからようやく、本格的な受験勉強が始まりました。
🟠 夜型のままの受験勉強
長男は夜型体質のまま、勉強を深夜に行う生活に。就寝は午前2時〜3時。
次の日も学校があるのに早く寝られず、親子で寝不足の毎日が続きました。
生活リズムの調整が苦手な長男に、「だったら昼寝をしなさい」と促し、それだけは守ってくれました。
最後の模試は偏差値53、C判定。私は不安を隠せませんでしたが、長男は落ち着いていました。
「高専の試験は独特だから。その対策はしっかりやった。模試の結果は気にしない。」
それを聞いて、私はこう思うようになりました。
**「もしダメでもいい。今までで一番頑張っている姿を見られた」**と。
🟠 そして、まさかの合格!
受験当日も、親子ともに淡々と迎えました。
試験後の長男は「英語が難しかった」と悔しそう。
私は正直、合格の期待をしていませんでした。C判定でしたし・・・
だから寮に入る準備などまったくしていませんでした。
しかし、結果は合格。
「自分で見る」とPCを開いた長男の顔が、満面の笑顔になった瞬間、私は信じられない気持ちでいっぱいでした。『嬉しい』と思えたのはその暫く後・・・。
✅ 新しいスタートへ
生活面の不安はまだまだあります。
でも、それ以上に今は希望のほうが大きい。
- 専門的な学びに夢中になれるかもしれない→長男が望む就職ができるかも・・✨
- 気の合う友人ができるかもしれない →人に執着しない長男に生涯の友ができるかも・・✨
- 将来を自分で考え始めるかもしれない →これから先のことを自分で決めていくのかな・・✨
ADHDである長男には、どうしても「わからない」「動けない」ことが多くありました。で
も、今回の受験を通じて、「やってみよう」と思える力が少しずつ育ってきた気がします。
✍ おわりに:親としてしてきたこと
思い返すと、たくさんの小さな工夫をしてきました。
- 年中から始めた算数の通信教育(少しずつ得意に)
- 九九をCDで先取りして「できる!」体験を与える
- タイピングの練習を通して、PCへの自信を育てる
すべてが順調だったわけではありませんが、**「少しでもできることを育ててあげたい」**という気持ちが、長男の中に小さな“土台”をつくったのかもしれません。
🌱 同じように悩む保護者の方へ
今つらくても、大丈夫。子供のために、と思って積み重ねていることは無駄にはならない。
子供にはペースがあること。子供が何かを決心した時、少しでも確率が上がるように、選択肢が広がるように・・
もちろん長男もこれがゴールではありません。新しいスタートです。
もし今回、不合格の結果だったとしても全く後悔はありません。長男が頑張れたことを糧に別のスタートラインに立てたと思います。
我が家のようなケースが、少しでもヒントや励ましになれば嬉しいです。
続きます・・
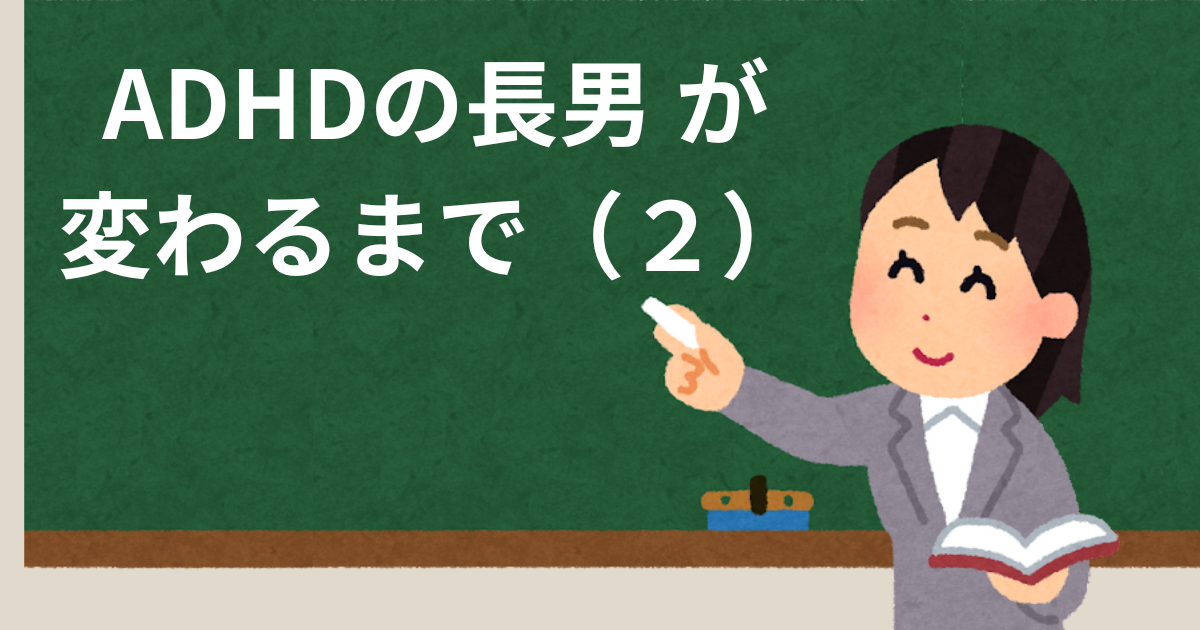

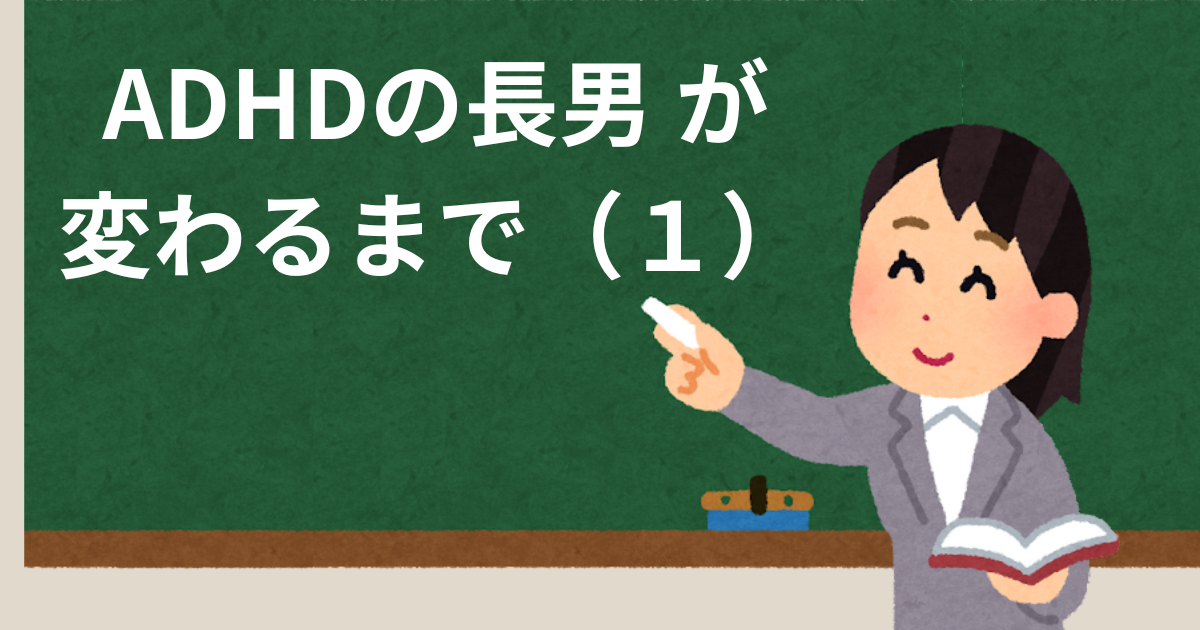
コメント