子どもの発達に「少し違うかも?」と気づくのは、多くの家庭では保育園時代ではないでしょうか。
私自身、長男が2歳の頃に園から「福祉に相談してみては」と声をかけられました。次男については、同じく2歳の頃に私が気になり園へ相談しました。
そこから市の支援員が定期的に園を訪れ、母親である私も同席して話を聞くようになりました。
この段階では、同じクラスのママたちも「なんとなく気づいている」ようでしたが、2歳前後では他の子に迷惑をかけることも少なく、特に問題視されることはありませんでした。
しかし年齢が上がるにつれて、周囲の目は変わってきます。
🍑 年齢が上がると、特性は「目立ってくる」
年少から年中、年長へと進む中で、発達の特性は少しずつ目立つようになりました。
特に次男は、自閉症の診断が年中の頃にすでに下りていました。
この頃になると、意地悪な子からいじられることもあり、またママたちの間でも「○○くんってちょっと…」と囁かれることが増えました。
そうなると、母親である私も居心地の悪さを感じることがありました。
そんなとき、私はあえて自分から切り出すようにしていました。
「うちの子、自閉症やってね。迷惑かけることがあったらごめんね」
先に自分から言ってしまうことで、余計な詮索や噂話を減らすことができたからです。
もちろん、中には意地悪なママもいて、わざわざうちの子の行動を話題にする人もいました。
けれど、診断が出ている以上、必要なときは病院名や診断内容まで話してしまった方が、私自身は気持ちが楽でした。
🍑 誰にどこまで話す?私なりの線引き
とはいえ、全てを誰にでも話すわけにはいきません。私は「相手によって話す内容を変える」という線引きを大切にしてきました。
- 夫には要点だけ伝える
夫は「深刻に考えすぎなくてもいい」と思っているタイプ。細かい相談をすると嫌がるので、私が思ったことや試したいことを要約して伝えるだけにしました。協力してほしいことだけお願いする。これくらいがちょうど良かったのです。 - 実家の母にはほとんど話さない
母はとても心配性で、さらに「こうすべき」と思ったら曲げない性格。もし細かく話すと「こうしなさい」と強く口を出されるのが目に見えていました。私は「後悔しないように自分の判断で育てたい」と思っていたので、あえて情報を精査して伝えない選択をしました。 - 仲良しママ友には浅めに
一番親しい支援級仲間のママとは愚痴を言い合える関係ですが、深い部分までは話しませんでした。逆にお互いの「困っている部分」をぶっちゃけ合うことで安心できたのです。
このように、すべてをオープンにせず、相手によってどこまで話すかを調整することが、結果的に自分自身の心を守ることにつながりました。
🍑 小学校に上がってからの変化
小学校に上がると、状況はさらに変わりました。
同じ学校の保護者たちは情報収集を大切にしていて、自然と「発達に特性がある子」ということが伝わる環境でした。
私はもう積極的に告知しなくても、「あの子はそういう子なんだな」という認識が広まっていました。
その中で、支援級に通う子のママたちとも自然につながり、信頼できる特定のママと親しくなることで安心感を持てました。
小学校時代は「うちはうち」という気持ちをより強く持てるようになり、他の子と比べるよりも「うちの子がどのように成長できるか」を第一に考えられるようになりました。
🍑 失敗談:ぶっちゃけすぎたケース
もちろん、全てがうまくいったわけではありません。
私が経験した「失敗談」を一つ紹介します。
ある日、クラスのママと何気ない会話をしていたときのこと。私は気が緩んで、つい愚痴をぶっちゃけすぎてしまいました。
私「昨日も全然寝なくて、手がかかって仕方ないよ。診断も出てるし将来も心配で…」
相手ママ「……そうなんだ(ちょっと引いてる感じ)」
その瞬間、「あ、これは重かったな」と感じました。
相手の表情を見て、こちらの気持ちがすべて伝わるわけではないことを痛感しました。
それ以降は、「愚痴や弱音は仲良しの支援ママ友だけに」と決めました。誰にでも正直に話せばいいわけではない。相手との関係や距離感を考えることが大切だと学んだのです。
🍑 まとめ:後悔しない告知の仕方とは?
発達障害に気づいたとき、周りにどう伝えるかはとても迷うテーマです。
私自身の経験から言えるのは――
- 全部隠す必要はない
- でも全部さらけ出す必要もない
- 相手と状況に応じて「どこまで話すか」を自分で選ぶ
ということでした。
結局のところ、「うちはうち」という姿勢で、後悔のない告知を選ぶことが一番大切だと思います。
必要な人に、必要なことだけを伝える。情報を精査し、自分の方針に筋を通していけば、子どもにとっても親にとっても心地よい関係が築けるのではないでしょうか。
→
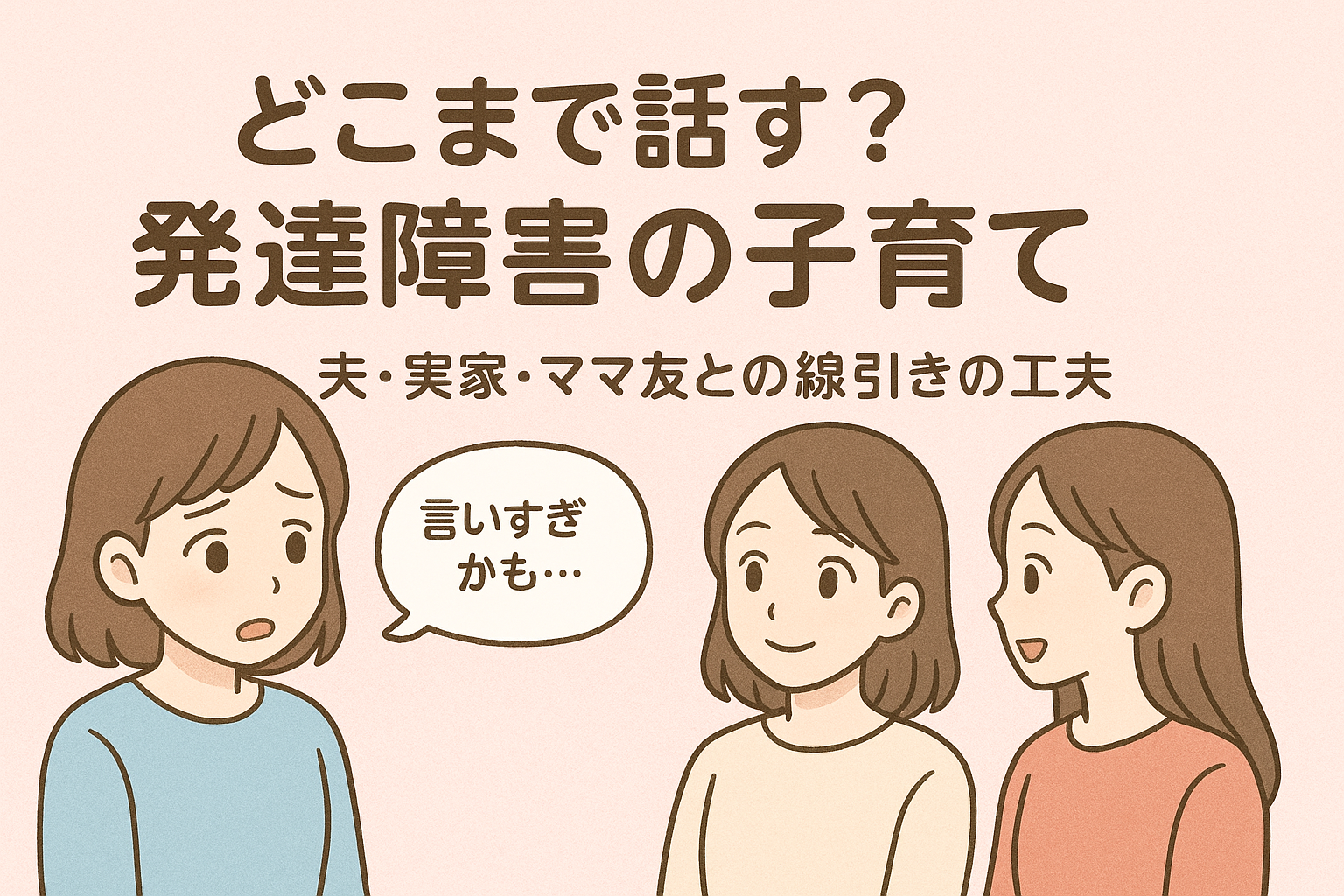
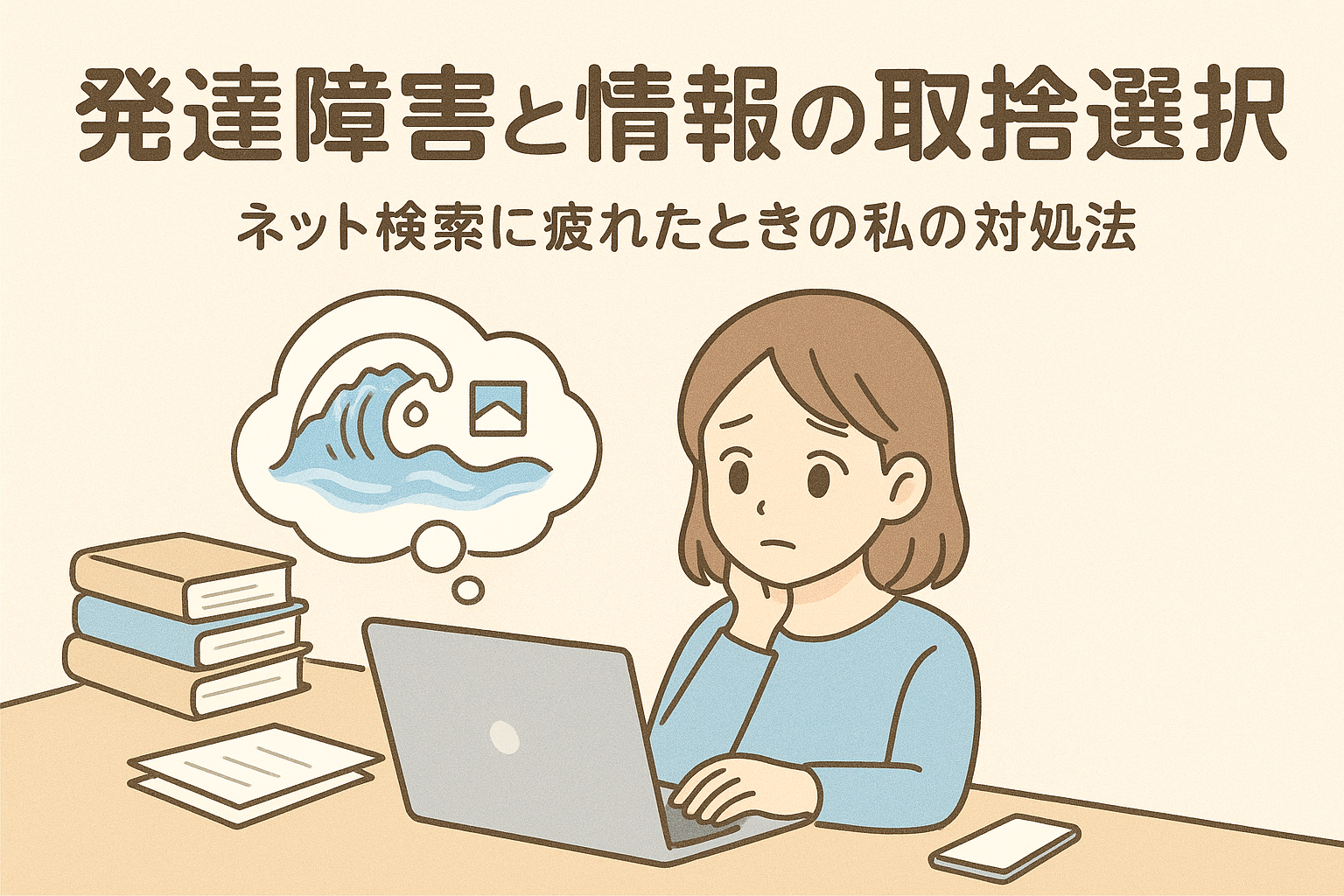

コメント