小学校から中学校へ上がるタイミングは、どの子にとっても大きな変化です。
特に、発達特性のある子にとっては「小学校ではできていたことが、中学校では急にできなくなる」という場面が多くなります。
わが家の次男(ASD、自閉症の特性あり)もその一人。
支援級から通常級へ進級し、7クラスもある大きな中学校に入学しました。ここでは、実際に困ったこと・事前に準備しておけばよかったこと・親としてやってよかった対応をまとめます。
🌀 入学してすぐに困ったこと
- 学校の広さと教室移動
中学校は校舎が広く、まるで迷路のよう。
次男は人の顔を覚えるのが苦手なため、案内してくれる友達も限られ、教室にたどり着けないことがありました。 - 教科ごとに先生が変わる混乱
小学校は担任制でしたが、中学校は教科ごとに先生が変わります。
名前も性別も覚えられない次男にとっては「誰がどの先生かわからない」状態。先生からの指示も頭に残りにくく、混乱の原因になりました。 - 提出物・教材管理の難しさ
各教科にノート・ワーク・プリントがあり、提出物のルールもバラバラ。
次男は「どの教科で何を出すのか」全く整理できず、毎日のように忘れ物や提出漏れが発生しました。
📝 支援級から通常級へ。期待と現実
「支援級から通常級に上がったのだから、少しは気にしてもらえるかな?」と母である私は思っていました。
しかし実際には、1クラス35人。担任の先生にとって一人ひとりの状況を把握するのは難しく、入学前に小学校の先生が行ってくれた申し送りも「誰が受けたのか不明」という残念な結果に。
入学後、担任との面談で次男の特性を伝えたものの、1学期の三者面談では全く共有されていないことが発覚しました。
――これは長男のときも同じだったので、ある意味「予想どおり」でした。
✅ わが家が実際に取り入れた工夫
- 教科ごとのメッシュ袋で管理
透明で中身が見える袋を教科ごとに分け、ノート・教科書・ワークをひとまとめ。
「この袋を持っていけば大丈夫」という形にすることで、忘れ物が激減しました。 - 提出物は“先回り”で予測
長男の時代の経験を生かし、教科ごとの提出物をあらかじめ予測。
(例:国語=ワークと漢字帳、英語=ノートとプリントなど)
「出される前から準備しておく」ことで、次男の混乱を減らしました。 - テスト週間のサポート
次男は「テスト週間」の意味自体がわかりません。
そのため「〇日にテストがあるよ」「このワークをやれば点が取れるよ」と具体的に伝え、できたらたくさん褒める。
これで少しずつテスト勉強の流れをつかみ、平均点を取れるようになりました。
🌱 成長を感じられた瞬間
成績や友達関係は「普通より少し下」程度かもしれません。
でも、次男にとっては 「毎日元気に学校に行ける」 こと自体が大きな成果です。
先日は「部活の体操服を忘れたから友達に借りた」と報告が。
自分から友達にお願いできたことに、親として本当に驚きました。
👩👩👧👦 ママとしての関わり方の変化
子どもが中学生になると、ママ友との付き合い方も変わります。
私はもともとママ友が少ない方ですが、今は「子ども抜きでも安心して会える友達」と少人数で付き合っています。
支援級のママ友とも、価値観が合う人とは交流を続けています。
小学校のときのような焦りはなく、「他の家と比べないで、自分の子どもの成長を喜べる」ようになりました。
🔮 今後に向けて
中学の間はまだ親が手をかけて世話をやく時期。
高校になると、子ども自身が自分の意見を持ち始めるでしょう。
それまでに、できるだけ多くの経験や選択肢を与えてあげたい。
次男が「自分らしい進路」を選べるように、親として支えていこうと思っています。
まとめ
- 中学入学は発達特性のある子にとって大きな試練
- 困りごとは「学校の広さ」「先生の多さ」「教材管理」など
- 事前準備(袋分け・提出物予測・具体的なテスト支援)が有効
- 「学校を嫌いにならず、毎日通える」ことを大切に
- 親自身も焦らず、子どもの成長を喜ぶ姿勢が必要
中学生活は大変ですが、親のちょっとした工夫で子どもの負担を減らし、安心して通える日々につながります。
→


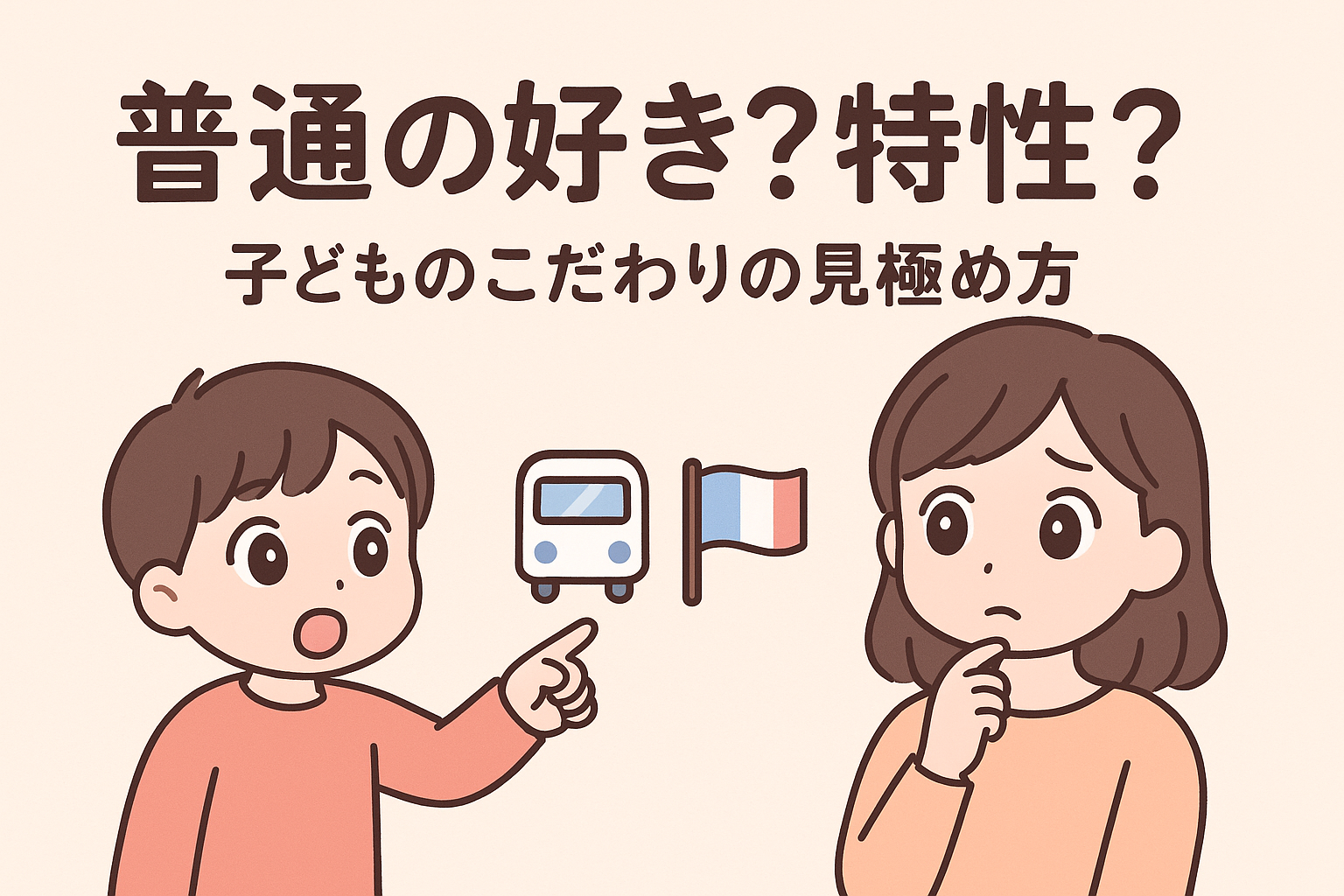
コメント