――私が迷いながら見えてきたこと
発達障害のある子を育てていると、「病院には行ったほうがいいの?」という迷いが必ず出てきますよね。
学校や保育園から勧められるのは、まず「ことばの教室」や通級指導教室など。確かにそこでサポートを受けるのも助けになるけれど、数年で終了してしまうことも多く、明確な見通しが立てにくいのが現実です。
一方で「病院で診断を受ける」ことには、メリットとデメリットがあると私は感じています。今日は、私自身が実際に悩みながら学んできたことを書いてみます。
🌻 病院にかかるメリット
私が思うに、病院を受診する一番のメリットは 「学校の対応が変わる」 ことです。
診断名があるかどうかで、支援の入り方は大きく変わります。担任の先生も「この子にはこういう特性がある」と前提を持って接してくれるので、配慮が受けやすくなります。
さらに、病院にかかると福祉サービスについても案内してもらえることがあります。放課後デイや療育など、親だけでは気づけない情報を得られるのは大きな利点です。
🌻 病院で感じる物足りなさ
ただ、病院の受診で「これで安心!」とは正直思えませんでした。
なぜなら、医師からもらえる説明は とても一般的 だからです。
「発達障害の子はこういう傾向がありますよ」と言われても、本を読んで勉強してきた私には、当たり前すぎて響かないことも多いのです。
「うちの子はこういう場面で困っているんです」と具体的に話しても、返ってくる答えは一般論に当てはめたもの。診察時間も短いので、深く相談するのは難しいな…と感じました。
そのうち「この受診、意味があるのかな?」と疑問に思うようになりました。
🌻 本当に頼りになる相談先はどこ?
私が欲しかったのは、「今の子どもの状態に合わせた具体的なアドバイス」でした。
そこで調べてたどり着いたのが、心理士さんとの相談です。残念ながら、私の住む市には子ども向けのリハビリ(OT・STなど)を行っている病院がなく、自分で探して心理士さんにお願いしました。
これは大正解でした。心理士さんは日常のエピソードをじっくり聞いた上で、「こういう対応を試してみましょう」と具体的に提案してくれるので、毎回とても実践的でした。
ただ、これも自分で動かないと医師から紹介されることはなく、「親が調べて希望を出す」必要があると痛感しました。
🌻 医師との関係はどうする?
正直に言うと、私の中で「医師は相談先としては優先度が低い」と感じています。
ただし、学校に対しては診断書や受診歴があることで支援が受けやすくなるため、“対学校用”としては通い続ける意味がある と割り切りました。
また、受診を続けていないと、医師から「そろそろ卒業してもいいですよね?」と軽く言われることもありました。こちらから「まだ必要です」とはっきり伝えることも大切です💦
🌻 相談先はひとつじゃなくていい
発達障害の子どもを育てていると、「どこに相談したらいいのか」がとにかく迷いどころです。
- 医師
- 心理士
- 保健センターの相談員
- 学校の先生やコーディネーター
- 放デイや療育のスタッフ
それぞれ役割が違うので、必要なときに、必要なところを選んで相談すればいい。完璧に頼れる「ひとつの場所」なんてないんだと思います。
🌻 ママ友との付き合い方も大事
もうひとつ大事なのは、ママ同士の関係。
同じ悩みを持つママと出会えたときは、とても心強いです。「ああ、うちだけじゃないんだ」と思えるだけで救われました。
ただ、子どもを挟むと関係が複雑になることもあります。気が合えばいいけれど、そうでないと逆にストレスになることも。私は「付かず離れず」がちょうどいいと感じています。
それから、発達に心配のないママ友とも距離感が必要だと思いました。大人数で集まるグループや噂好きの人たちの中では、支援を受けているうちの子の話題が出てしまうこともあると聞きます。自分の精神を守るためにも、付き合い方を調整することは大切でした。
🌻 まとめ:頼れる場所を、自分で選んでいい
発達障害のある子を育てる中で、「病院に行くべきか」は悩めるテーマかもしれません。
私がたどり着いた答えは、
- 医師は“対学校”として必要
- 具体的なアドバイスは心理士やセラピストの方が得意
- 相談先はひとつに絞らず、必要なときに選べばいい
- ママ友との距離感も大切
ということでした。
最初から完璧な答えなんてありません。子どもの成長とともに、親の立ち回りも変わっていきます。
「今の私と子どもに必要な相談先はどこだろう?」――そうやって柔軟に考えながら歩んでいけたら、それで十分だと思っています!
→🧐自閉症ってどんな特性?良いところ・困るところを知ろう


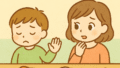
コメント