〜偏食・感覚過敏にどう向き合う?〜
🥄「食べる・食べない」が読めない次男
わが家の次男は、自閉症の特性があります。
食事に関してはとても不思議で、「好き嫌いは少ない」のに偏りが目立つ子です。
- 幼児期:朝は毎日「納豆巻き」しか食べなかった
- 小学生になって:一時期は毎朝「カロリーメイト」にハマる
- 大好物の唐揚げでも「今日は食べない」と一口も手をつけない
- 大好きな肉炒め(焼肉のたれ味)を出しても「いらない」とスルー
- 休みの日はお昼ごはんを食べないこともある
- かと思えば、驚くくらいモリモリ食べる日もある
食べる内容も、量も、とても歪で予測できません。
親としては「何を食べてくれるのか」「栄養は足りているのか」と心配になる日々です。
🥄 発達障害の子に多い「食の困りごと」
発達障害のある子どもは、食事にまつわる困りごとを抱えることが少なくありません。
代表的なものには次のような特徴があります。
- 偏食が強い
白いご飯しか食べない、決まった銘柄のパンしか食べない、など特定の食品にこだわる。 - 感覚過敏
食感(ぬるぬる、ザラザラ、固い、ねばねば)が苦手で受け付けない。
味や匂いの刺激に敏感で、一般的には人気の料理でも食べられない。 - 感覚鈍麻
逆に刺激を感じにくく、強い味付けやスナック菓子を好むケースもある。 - 気分や習慣に左右されやすい
昨日食べられたものを今日は全く食べない。
ルーティンや一時的なこだわりで「毎日同じもの」しか受け付けないこともある。
わが家の次男も、この「気分や習慣に左右されやすいタイプ」です。
🥄 偏食の背景にあるもの
「どうしてこんなに食べたり食べなかったりするんだろう?」と疑問に思うかもしれません。
発達障害の子どもに偏食が多いのには、いくつかの背景があります。
- 感覚処理の特性
味覚や嗅覚、食感の感じ方が普通と違うため、「本人にとって食べられるかどうか」の基準が独特になる。 - 見通しのつけにくさ
気分や体調をうまく表現できず、「今はいらない」「食べられない」と拒否してしまう。 - こだわりや安心感の追求
同じものを食べ続けることで安心感を得る時期がある。逆に「今日は違う」スイッチが入ると受け付けなくなる。 - 身体的な要因
胃腸が弱い、便秘がある、嚥下のしづらさがあるなど、体調の影響で食べたり食べなかったりする。
🥄 親としての戸惑い
「せっかく作ったのに一口も食べない」
「昨日まで喜んで食べていたのに、今日は完全拒否」
「お昼を全く食べないなんて大丈夫なの?」
日々、親としては戸惑いと心配の連続です。
特に栄養バランスや体の成長に直結することなので、焦りや不安も大きくなります。
次男がまだ保育園に通う時代はどうして良いか真剣に悩んでいました☺️
🥄 どう向き合えばいいの?
完全にコントロールするのは難しいですが、工夫次第で少し楽になることもあります。
「食べない日」があっても大丈夫と考える
一食や一日くらい食べなくても、体調が良ければ大きな問題にはなりません。
「今は食べないけど、必要なときは食べる」と割り切る視点も大切です。
好きな食品をベースにする
毎日カロリーメイトでも、納豆巻きでも、それで栄養が一部補えるなら安心材料に。
「食べられるもののストック」を持っておくと親の気持ちも軽くなります。
「無理強いしない」を徹底する
嫌がっているときに無理に食べさせても逆効果。
「食べない=悪いこと」ではなく、「食べられたらラッキー」と思えるくらいがちょうどいいです。
医療や専門職に相談してみる
管理栄養士や小児科、発達外来などで相談すると「代替食品」や「サプリメント」などの情報が得られることもあります。
🥄 偏食が教えてくれること
次男を見ていると、「食べる・食べない」にはその子なりの理由が必ずあると感じます。
感覚的なもの、体調的なもの、心理的なもの…。
大人から見れば「わがまま」「気まぐれ」に見えても、本人にとっては「本当に今は受け付けない」だけなのです。
そして、時期がくれば食べられるようになることもあります。
幼児期に納豆巻きしか食べられなかった次男も、今ではいろいろな食品に挑戦できています。
私も幼児期の食事はとても悩みましたが・・。そのうち1日トータルで量が入っていればいいかな、と気楽に考えるようになりました。体重が減っていったりしたら心配しよう、とルールを決めたら楽になりました!
🥄 まとめ
発達障害のある子どもの食事には、偏食や感覚過敏がつきものです。
「好き嫌いが多い」というより「感覚やこだわりに左右されやすい」のです。
- 昨日食べたものを今日は食べない
- 同じものばかり食べ続ける
- 全く食べない日もある
親としては心配になりますが、まずは「子どもの特性」と受け止めること。
無理に正そうとするより、安心して食べられるものを軸に、少しずつ広げていければ十分です。
「食べない」ことに悩むより、「どうやったら安心して食べられるか」を一緒に探すことが、子どもにとっても親にとっても楽な道だと思います。
→次の記事 「発達障害の子ども、病院にかかる必要はある?」


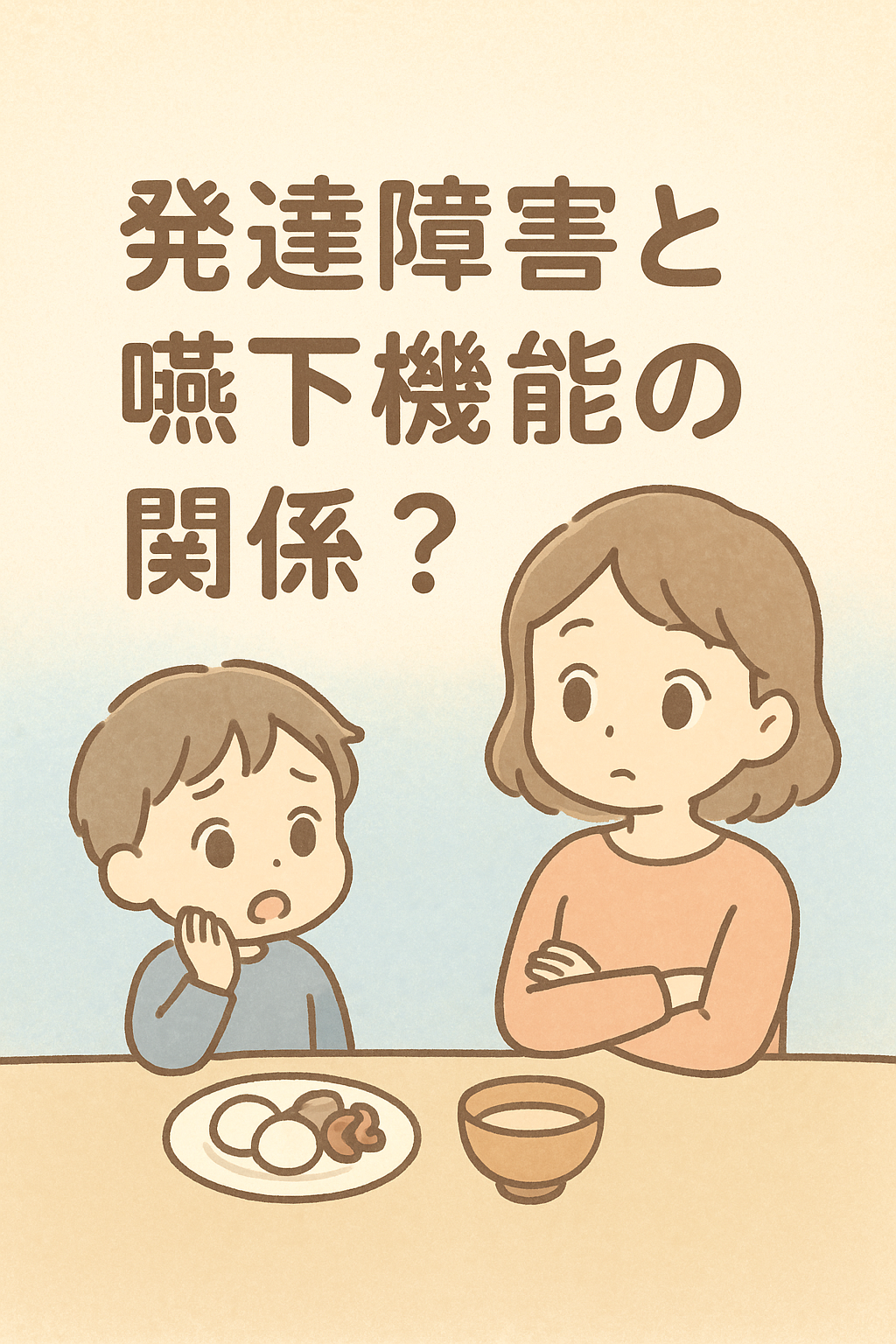
コメント