〜発達障害の子どもを育てる母としての気づき〜
🧐 職場で目につく「特性のある大人たち」
子どもの発達について真剣に考えるようになってから、職場で出会うスタッフの中にも「特性」を持っていそうな人が多いことに気づきました。
私の職場は、さまざまな職種と多くのスタッフが関わる場所。年齢も経験も幅広く、個性豊かな人が集まっています。
でも、どの職種にも必ず数人はいます。
- 空気が読めない
- 相手の意図を汲み取れない
- 上手い立ち回りができない
私が子どもに言いたくなるような言葉を、そのまま投げかけたくなる場面がよくあります。
「計画を立ててから動きなさい」
「先のことを考えて行動して」
「チームで動く時は周りの動きを見て」
「自分のことばっかり考えない」
「見ればわかることに何で気がつかないの?」
🧐 職場では誰も注意しない現実
家庭では、こういう場面で親が指摘できます。
でも職場では違います。
誰も直接「それは困る」とは言いません。ただ一緒に組むことを避けられたり、会話から外されたり、無視されたり……。気づけばその人は孤立し、弱い立場に追い込まれているのです。
社会は、学校のように「あなたのここを直しましょう」と手を差し伸べてくれる場所ではありません。
不器用さや特性がある人は、自分で気づき、修正していかないと、静かに生きづらさが積み重なってしまうのです。
🧐 子育ての参考にする「社会の縮図」
そんな職場の人間模様を見ていると、私は自然と子育ての参考にしていました。
発達障害のある子どもを育てていると、日常生活や学校生活を乗り切るためのサポートで手いっぱいになりがちです。
でも実際には、その先にある「社会でどう生きるか」まで視野を広げる必要があります。
🧐 社会に出てから困らないために、今から育てたい力
私が職場で感じた「特性の強い人がつまずくポイント」から逆算して、子どもに身につけさせたいと思ったのは次のような力です。
- 計画性を持つ練習
宿題や課題、自由研究など「期限のあること」を計画的に進める練習を、家庭で少しずつ。
最初は親がスケジュールを立て、一緒に進める形でもOK。 - 相手の立場を想像する力
会話や遊びの中で、「相手はどう思うかな?」と問いかけてみる。
小さなことでも相手視点を意識する習慣は、大人になっても生きる。 - 自分の動きを周囲に合わせる意識
家庭内でも「みんなで準備」「一緒に片付け」の時間をつくる。
「自分だけのペース」から「みんなのペース」に切り替える練習になる。 - わからないことをそのままにしない習慣
「聞くのが恥ずかしい」よりも「わからないまま動くほうが困る」と気づかせる。
質問の仕方を教えるのも大事なスキル。
🧐「社会に出るまでに直すべきこと」はある
発達障害のある子どもには、得意不得意の差が大きくあります。不得意な部分を完全に無くすことは難しいかもしれません。
でも、最低限「これだけは社会に出るまでに身につけておいたほうがいい」という力は確かにあります。
職場で孤立している大人たちを見ていると、それは決して学力や資格だけではないと強く感じます。
むしろ、周囲との関係性を保つための「コミュニケーション力」や「自己調整力」のほうが重要です。
🧐 家庭でできるのは「予防」と「練習」
職場で孤立してしまった大人は、残念ながらすぐに改善するのは難しいことが多いです。
だからこそ、子どものうちに「予防」として社会で生きる練習を少しずつ積み重ねたい。
- 家庭の中で、簡単な役割や責任を与える
- 自分の行動が周りに与える影響を伝える
- 失敗してもフォローしつつ、「どうしたら次はうまくいくか」を一緒に考える
これらはすぐに成果が出るわけではありませんが、確実に子どもの「社会力」を育てます。
☺️ 最後に
私は職場で、特性の強い人が苦労している姿を何度も見てきました。
そのたびに「うちの子にはこうなってほしくない」というより、「この人がもっと早く学べていたら良かったのに」と思います。
とりあえず、だからこうしようと思いつくことはその時にはありません。私が仕事の中で過ごす時、そんな場面を目撃してはいろいろ考えていれば良いかな、と。私の中に色々な考えがあれば子育ての日常の中で自然に反映されていっています。
具体的にこれだけは、と思うのは『ハキハキとした挨拶』『ありがとうございます・申し訳ありませんなどの言葉がが自然と出ること』の2点。これだけです。
子育ては、今の学校生活を乗り切るためだけではありません。
10年後、20年後の社会で自分らしく生きられるように、小さな習慣づくりから始めたい──そう強く感じています。
→🦑発達障害と嚥下機能の関係とは?

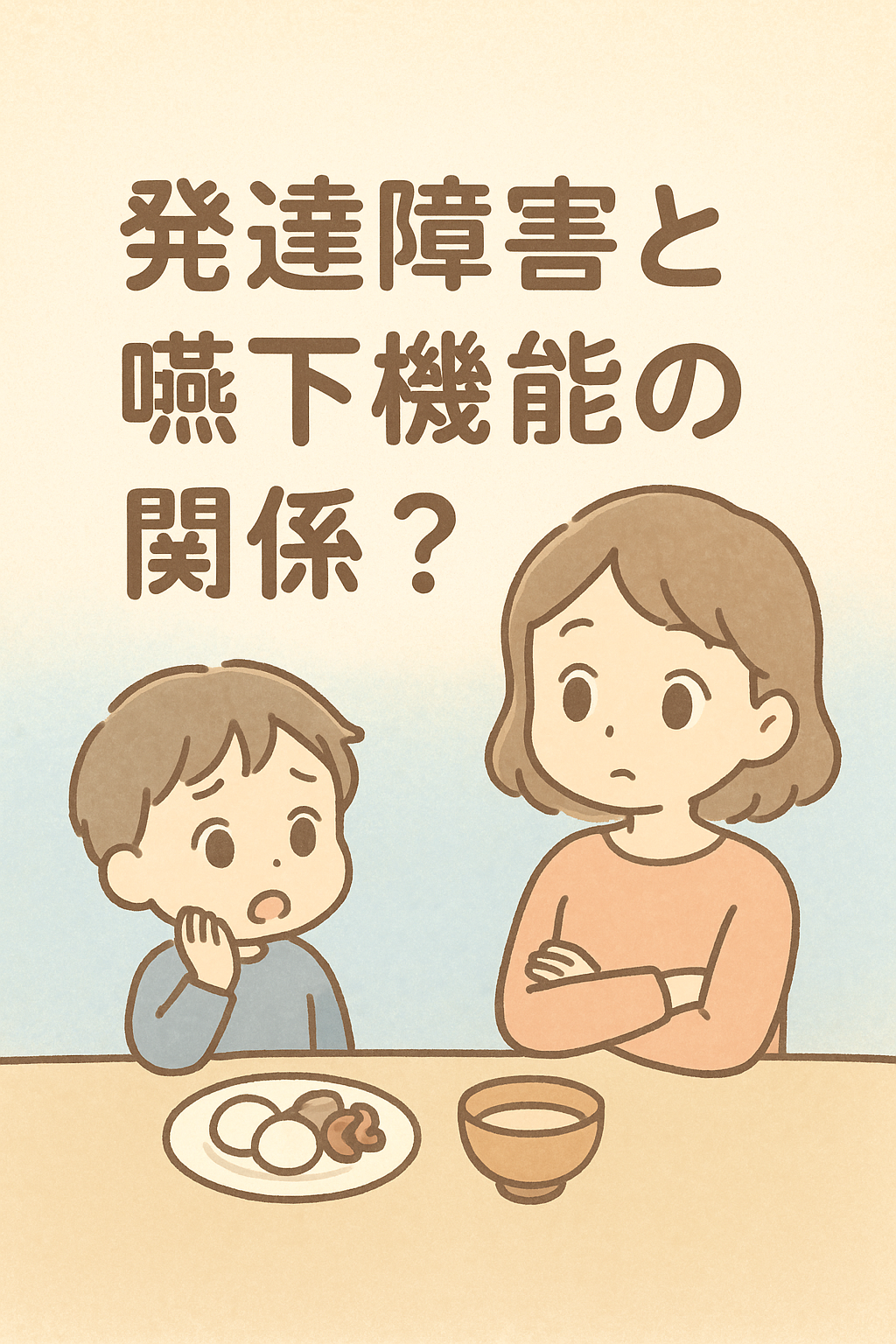
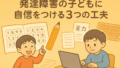
コメント