〜九九・ローマ字・漢字検定で変わった息子〜
🐎「みんなより遅れてしまうかも…」という不安
発達障害のある子どもは、学校の授業スピードに合わせるのが難しいことがあります。
特に、九九・ローマ字・漢字のように「覚える量が一気に増える単元」は、つまずきやすいポイントです。
うちの次男も例外ではなく、普通のペースでは到底追いつけないと感じていました。
そこで私は、「始まる前から少しずつやっておく」作戦に切り替えました。
結果的に、この方法が息子の学習の自信を大きく育てることになったのです。
九九は2か月前から毎日CDで耳に入れる
九九は小学2年生で本格的に学習します。
学校では、みんなで競いながら覚え、小テストを繰り返します。
普通の子にとっても負担が大きいこの単元、次男にとってはなおさらハードルが高いものでした。
私は、授業が始まる2か月前から九九のCDを毎日流しました。
「お風呂の時間」や「寝る前」など、生活の中に自然に組み込んでいきます。
まだ学校で習っていないことをやるのは面倒に感じるかもしれませんが、
「学校で始まる頃にもう覚えていたらすごいよ!」と励まし、
1つ覚えたら大げさなくらい褒めました。
こうして先取りしておいたおかげで、授業が始まるころには自信を持って九九を発表でき、
「僕、できる!」という気持ちが芽生えました。
ローマ字は好きなもので遊びながら
ローマ字は、小学校3年生ごろに軽く習います。
でも授業では時間をかけず、習った直後でもしっかり覚えていない子も多いのが現状です。
次男も同じで、授業で習っただけでは身につきませんでした。
そこで私は興味のあるもので練習させることにしました。
- 好きな漫画のかっこいいセリフをローマ字で書く
- 流行りの歌の歌詞をローマ字で書いて読ませる
- 慣れてきたら逆に日本語をローマ字で書かせる
遊び感覚で続けるうちに自然と覚え、次のステップとしてタイピング練習に進みました。
タイピングは教室でゲーム感覚に
正直、私は自宅でタイピング練習をやらせることに少し抵抗がありました。
でも、これからはパソコンを使った課題提出も増えていく時代。
早いうちに慣れておくことは大きな武器になります。
そこで、近所のパソコンスクールに通わせ、
ゲーム形式で楽しくタイピングを練習できる環境を用意しました。
最初はおそるおそるでしたが、上達してくるとどんどん夢中になり、
高学年ではクラスメイトから「タイピングすごいね!」と一目置かれる存在に。
これは本人の自尊心を大きく高めるきっかけになりました。
漢字検定で「苦手」が「得意」に変わった
次男は、ひらがなを書き始めたころから字が歪んでおり、漢字も苦手。
小学4年生のとき、学校で受ける漢字検定(強制参加)がありました。
私は、検定1か月前から過去問題集を用意し、毎日1回分ずつ練習させました。
繰り返すうちに点数が安定して上がり、本番では高得点で合格。
この成功体験が大きな転機となり、
「僕、漢字得意かも!」と本人が思えるようになりました。
以後、国語全般に前向きに取り組むようになったのです。
🐎 成功の鍵は「早め」と「楽しく」
今回ご紹介した3つ(九九・ローマ字&タイピング・漢字検定)は、
どれも本人が苦手になりそうな単元を、始まる前から少しずつ準備するという共通点があります。
また、「褒める」「遊び感覚でやる」「成功体験を作る」こともポイント。
失敗や苦手意識が先に来てしまうと、やる気を取り戻すのは大変です。
逆に、「できた!」「すごい!」という経験は、長く自信として残ります。
まとめ
発達障害の子どもにとって、学校の学習ペースは速すぎることがあります。
でも、ちょっと先回りして、本人に合った方法で取り組むだけで、
学習の自信は大きく変わります。
九九、ローマ字、漢字検定。
この3つは、うちの次男が「苦手」から「得意」へと変わるきっかけになりました。
同じようにお子さんの学習に悩む方は、ぜひたくさんのことをいろいろ試してみて下さい。その中でいくつかうまくいく事があれば良いと思います!
→🏢職場で気づいた「特性」と社会で生きる力💪
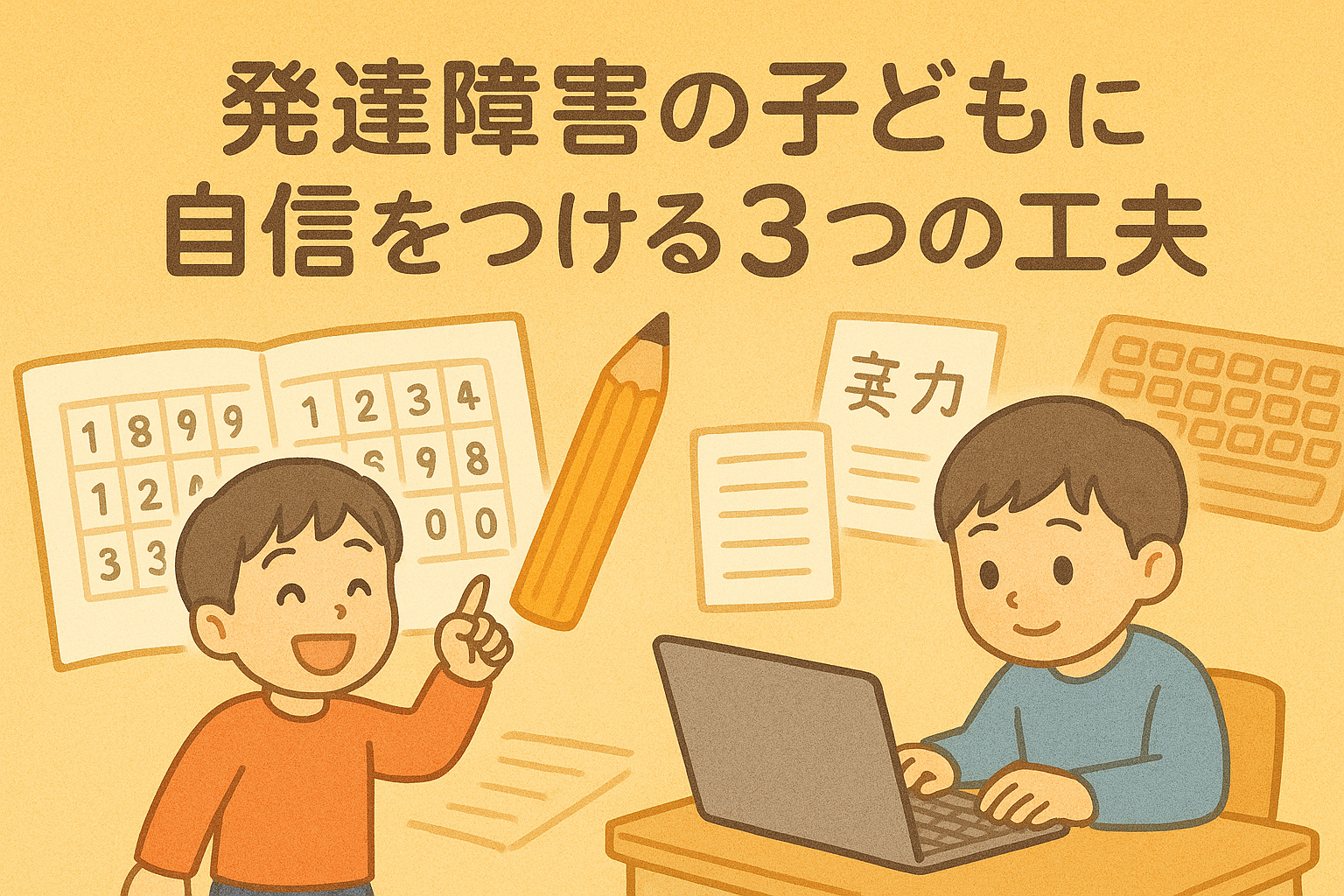



コメント