🌻 保育園では“自動的”だった支援が、小学校で消えた
長男は、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれる発達特性があります。保育園時代には、3ヶ月に一度、福祉の担当者が園に来てくれて、面談の案内も向こうからありました。私はその都度、言われたことを守りながら、園と支援機関に任せておけばなんとかなると思っていました。
でも、小学校に入学したその瞬間、支援の流れは突然止まってしまいました。
「誰も何も言ってこない」
「え?今後どうしたらいいの?」
あのときの戸惑いは、今でもよく覚えています。
🌻 何をどう相談すれば? 支援の“迷子”になった日々
困って担任の先生に相談したところ、「役所に聞いてみてください」と案内され、役所で紹介されたのが福祉センターでした。
実際に訪ねてみると、そこは保育園時代に面談をしてくれていた場所。ただし、小学生になると担当部署が変わるそうで、新たな職員さんとまた最初から面談をすることになりました。
3時間近くにおよぶ親の聞き取り面談。長男が生まれた時からの育ちや、これまでのエピソードを一から話すことになりました。
「前回までの記録って、引き継がれていないの?」
そう思わずにはいられませんでした。
面談の最後は、「また何かあったら相談してくださいね」で終了。
その後も定期的に足を運んだものの、「お母さんが無理しないようにしましょう」「成長を見守りましょうね」と言われるばかりで、具体的な支援にはつながりませんでした。
🌻「お母さん、無理しないで」と言われ続けた不安
長男は3年生になるころ、学校がどんどん苦手になっていきました。理由の一つは、担任の先生が感情的になりやすいタイプだったこと。怒鳴られるとすぐに萎縮する長男には、つらい環境でした。
次第に、夜尿やチック、そして頭痛まで現れるようになり、これはもう精神的にも身体的にも限界かもしれない、と思いました。
担任の先生に特性のことを話し、配慮をお願いしましたが、親に対しては穏やかに接してくれる方だったので、「怒らないでほしい」とまでは切り出せず……。
私は、何度も「これは、親としてもっとできることがあるはず」と自問するようになりました。
🌻小児科から大学病院へ──支援が動き出したきっかけ
ある日、「頭痛が心配で詳しい検査を受けたい」と、行きつけの小児科に相談してみました。
本音を言えば、「大学病院に紹介してもらえれば、発達の専門外来につながるかもしれない」という希望もありました。
すると先生は、私の気持ちをくんでくださったのか、「それなら紹介状を書きましょう」と言ってくれたのです。
こうして長男は大学病院を受診することに。そこからが大きな転機でした。
🌻「診断」があると、学校の対応が変わった
大学病院での発達検査の結果、正式な診断がつきました。
その情報をもって再度学校へ伝えると、対応がまるで別物に。
「大学病院の医師がこう言っていました」と伝えると、先生方の姿勢が一変。
それまで“後回し”にされていた印象だった支援や配慮が、急に真剣に扱われるようになったのです。
後で知ったのですが、福祉センターには大学病院の医師が月に一度来ているとのこと。診断を通して、支援のネットワークがようやくつながってきたように感じました。
🌻やっぱり「動いてよかった」──親の直感を信じて
4年生からは、通常学級に在籍しながらも、発達特性についての申し送りがしっかりと行われていて、担任の先生も支援の知識が豊富な方でした。
学校での声かけや、クラスでの配慮も自然なかたちで行われ、長男の表情にも少しずつ明るさが戻っていきました。
「どこまで大学病院での診断が影響しているのかは分からない」
でも、親が動いたことで、確実に何かが変わったと思っています。
あのとき、「しょうがないよね」と学校に任せていたら、今の環境はなかったかもしれない。
思い切って小児科の先生に相談して、本当に良かったと思っています。
💐 最後に:迷ったときは、「親の違和感」を信じていい
支援が突然切れて、誰にも頼れないように感じること。
相談しても「お母さんが無理しないで」と言われるばかりで、進展がないこと。
そんな経験をしたからこそ、私は今、強く思うのです。
「親が感じた違和感は、子どもを守るためのセンサーなんだ」と。
動いてみること、あきらめずに相談し続けること。
それが、少しずつでも確実に、支援をつなげていく一歩になると信じています。
→🐣子どもの発達に悩むママたちへ──家庭の方針も、つながり方も、人それぞれでいい🥚
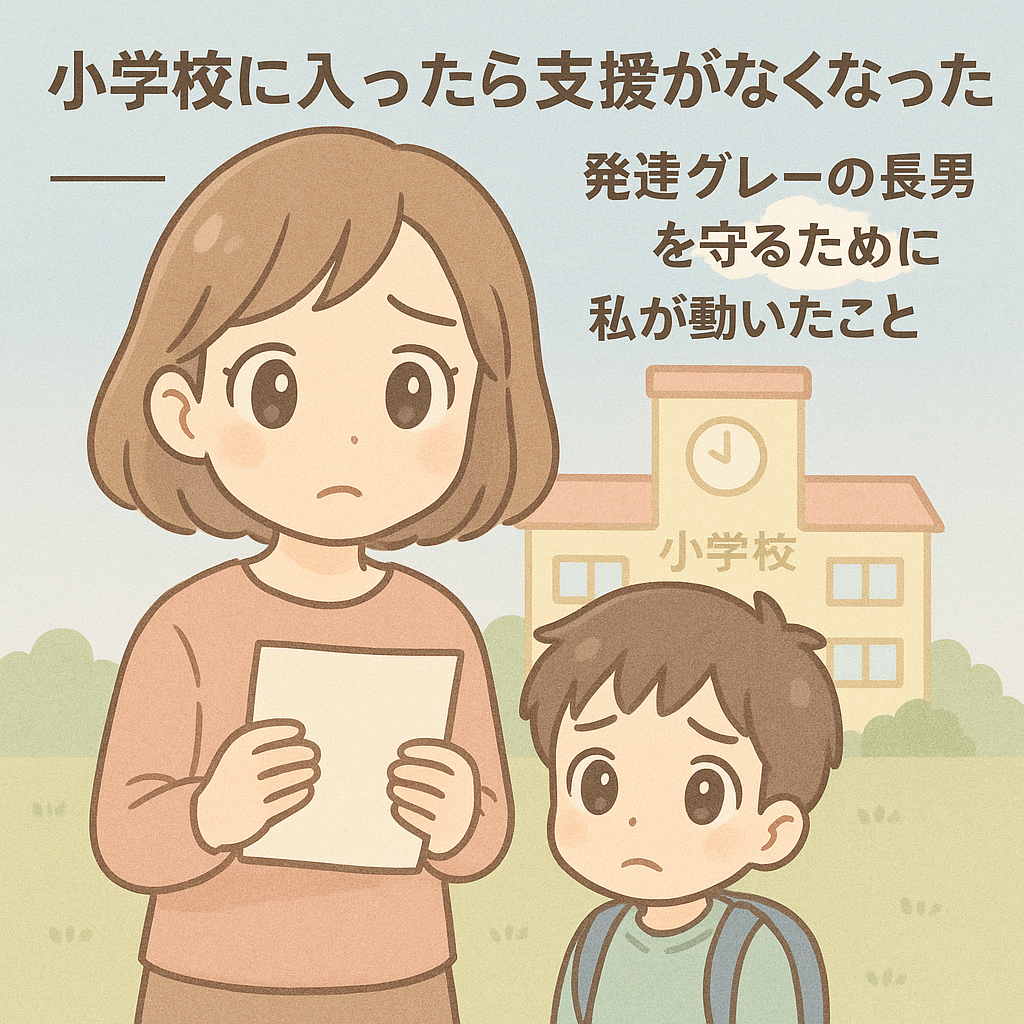
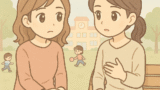

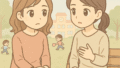
コメント