発達障害のある長男と次男。子どもたちを大切に育てる日々の中で、何より大切だったのは「母である自分が追い詰められないこと」でした。
最初は、とにかく目の前のことで精一杯。長男はADHD(不注意優勢型)、次男は自閉スペクトラム症。それぞれ違う特性を持っていて、支援も対応もまったく違う。けれどどちらも、とても愛しい、かけがえのない存在です。
❤️ 一番の理解者は、病院の心理士さん
子どもたちが発達障害の診断を受けた頃、私は気が張り詰めていました。
診断を受けたからといってすぐに何かが変わるわけではなく、どう接していいかも分からず、「この子たちの将来はどうなるんだろう」と不安ばかりが大きくなっていきました。
そんな中、病院の心理士さんがかけてくれた言葉は、今でも忘れられません。
「お母さんが追い詰められてしまったら、家庭はうまく回りませんよ。まずは、お母さん自身の心と暮らしが安定することを優先してくださいね。」
この言葉に、私は少し肩の力を抜くことができました。
❤️ 特性があっても、「できないこと」はそんなに気にしない
幼児期の子どもたちは、発達の凸凹が顕著でした。次男はひとり遊びばかりで、集団行動が難しい。長男はすぐに気がそれて、忘れ物も多く、生活に支援が必要でした。
でも、私は「できないこと」を必要以上に気にしないようにしました。
もちろん困りごとはサポートしました。でも、「今はまだできないだけ」と思えば、気持ちがラクになります。そして「好きなこと・得意なことを伸ばせばいい」というスタンスで、子どもたちと関わるようになりました。
❤️ 職場にも、ほどよく伝える
私が働いている職場には、子どもたちが発達障害であることを伝えてあります。
難しければ具体的な診断名までは言わなくても、「子どもに少し支援が必要で」と伝えておくだけで、理解が得やすくなります。
全部隠して頑張りすぎてしまうよりも、ほんの少し「言葉で伝えること」が、後の自分を救ってくれるのだと感じています。
❤️ 夫婦が助け合い、子どもたちを平等に愛する
我が家では、「夫婦で助け合うこと」と「兄弟を同じように愛すること」をとても大切にしています。
長男も次男も、それぞれ違う特性を持っています。でも、比べたり、優劣をつけたりせず、どちらにも「大好き」と伝えるようにしています。
時には過保護になってしまうこともありますが、それでいいと思っています。子どもたちに「無条件に愛されている」と感じてもらえることが、自己肯定感を育む第一歩だと信じています。
「夫婦で助け合う」というのは平等ではありません。子育て8割母です💦
学校や病院、福祉施設等書類類なんかも全て母の仕事です。
これは夫の理解が悪い(?)から。夫は基本的にほっておいても大丈夫だろう、との考え。
だけど私が「こうしたい」ということは尊重してくれます。だから報告はするけど細かいことは言いません。夫にしてほしいことだけを伝えます。(保育園の送り迎え、放ディの見学等伝えたら一緒に行ってくれます それ以上は期待していない・・・)
でも私ができないこと。子供達とゲームしたり遠くの公園に行ったり楽しそうにしていました。
❤️ 母は、笑っていていい
子どもたちのことで頭がいっぱいになる日々。だけど、私はなるべく「笑っている母」でいようと心がけてきました。
もちろん、毎日うまくいくわけではありません。だけど、気分転換の方法をいくつか持っておくと、少しだけ元気が戻ってきます。
私の場合は、大好きなコーヒー☕️。子供が小さい頃、週末にショッピングセンターへ出かける時、夫に「15分だけいい?」と声をかけて、スタバで一人時間をもらいます。(夫が一人で子供を見るのは長時間は無理でした)
その短い時間に、心がすーっと整っていく感覚があります。
❤️ 家事も、節約も、ほどほどでいい
「子どもたちの将来のために…」と、つい節約や家事に力を入れてしまいがちですが、私は必要以上に無理をしないと決めました。
- 掃除は週末にまとめて
- 冷凍食品やお惣菜を活用
- 少し家が散らかっていても気にしない
- ご飯作りがしんどい日は、外食やテイクアウトでもOK
家事の優先度は、あくまで「母が笑っていられるかどうか」で決めています。
❤️ 自分に甘くすること、罪悪感は持たないこと
発達障害のある子の子育ては、想像以上にエネルギーがいります。だから私は、意識的に自分に甘くするようにしています。
- 疲れたらちょっとお昼寝をする(子供が幼児の時はとても無理でしたが💦)
- 自分のための少し高いチョコを購入 コーヒーも美味しいものを買います!
- 通勤電車、片道15分が毎日の一番自由な時間でした・・音楽を聴いたり、本を読んだり🎵
そうやって「なるべくご機嫌な母」でいられる時間を作ることが、家族全体の雰囲気を明るくしてくれると実感しています。
❤️ 子どもの未来を信じて、今日できることを少しずつ
今はまだ小さな子どもたち。でも、ふとした瞬間に「この子の将来」を想像するようにしています。
「これができたらいいな」「こういうことが好きかな」——
その“想像”が、次の支援のヒントになり、“信じる気持ち”につながります。
❤️ 最後に ❤️❤️
発達障害の子育ては、マニュアル通りにはいきません。でも、母である自分が潰れてしまっては、何も始まりません。
「すこし甘め」「すこしゆるめ」で、でもしっかり子どもを愛していく。
それが、私がたどり着いたバランスの取り方です。
→🏫小学校に入ったら支援がなくなった💦──発達グレーの長男を守るために私が動いたこと(長男)

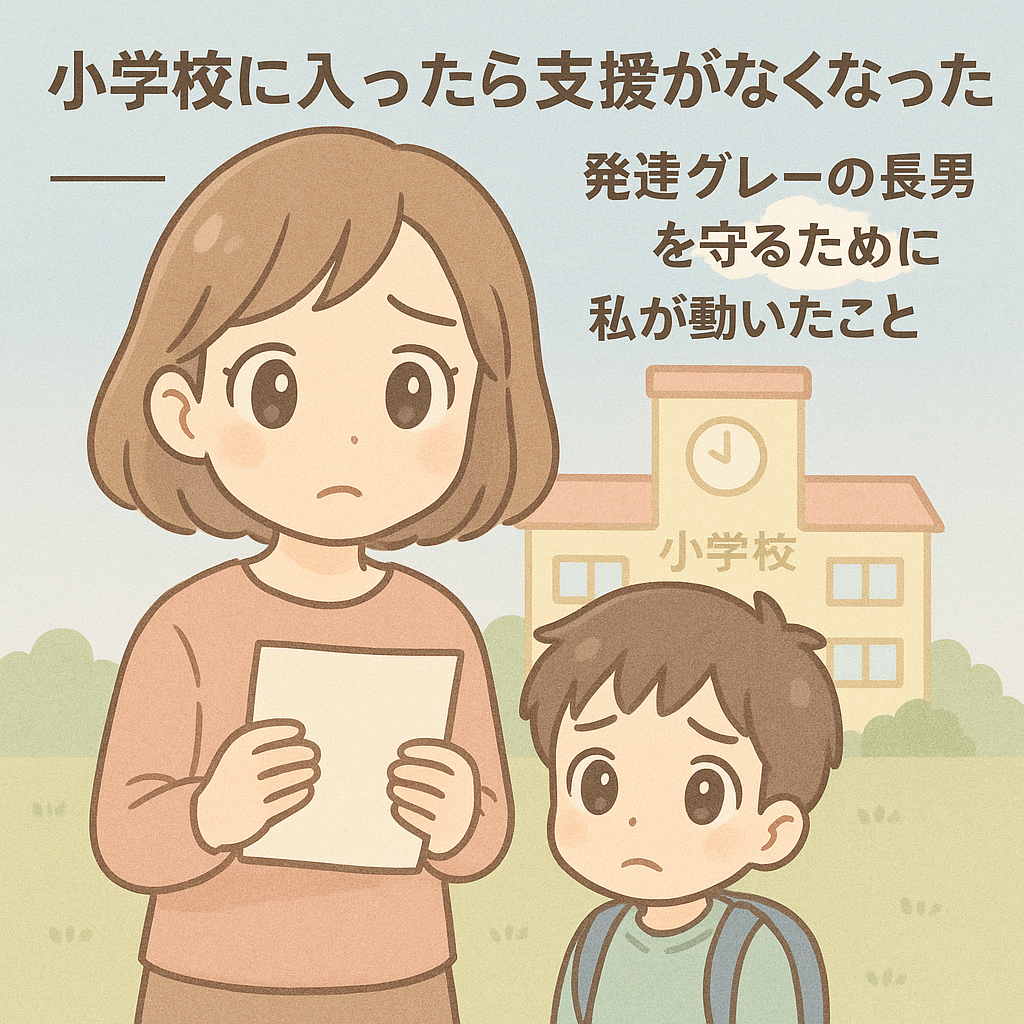

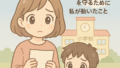
コメント