私の子どもたちは、次男が「自閉症スペクトラム(ASD)」、長男が「ADHD(注意欠如・多動症)不注意優勢型」という診断を受けています。どちらも「発達障害」と呼ばれる枠組みの中にありますが、その特性も、関わり方もまったく違います。
この記事では、家庭での経験をもとに、ASDとADHDの特性、対応の工夫について紹介します。お子さんの育て方や接し方に悩む保護者の方のヒントになれば幸いです。
◆ 次男の特性:自閉症スペクトラム(ASD)
自閉症スペクトラムとは、「コミュニケーションの苦手さ」や「こだわりの強さ」「感覚の敏感さ」などがみられる発達の特性です。スペクトラムという言葉の通り、特性の現れ方や強さは人それぞれです。
◯ 主な特性(次男の場合)
- マイペースで一人遊びが好き
小さい頃から集団より一人遊びを好みました。砂場や工作が大好きで、自分の世界で遊ぶ時間が一番楽しい様子でした。中一になった今も学校や部活は楽しんで参加しますが家に帰ると自分の世界で何時間も過ごします。友達と遊びに行こうとはしません。でも楽しそうです☺️ - 人との関わりが少ない
本人は笑顔で遊んでいても、周囲の子と会話をしたり、一緒に遊んだりすることは少なめ。言葉も通じ合っているようで噛み合わないこともありました。人の顔が区別できず特に仲の良い友人以外は名前もわからないまま過ごす事が多いです💦 - 感覚が敏感
服のタグが気になって着替えを嫌がったり、特定の音に強く反応することもありました。反対に、ケガをしても痛みを訴えにくいときもありました。喉の渇きを感じないため、幼児の時は保育園で毎年のように熱中症になっていました・・・🥲 - こだわりが強い
納豆巻きしか食べない時期があったり、自分の作った“象形文字”を家中に貼って「これが僕の字」と主張するようなことも。幼児の頃は保育園への登校準備に時間がかかるくらいの悩みでしたが、成長してくると生活の妨げとなるような深刻な悩みもあり困りました・・😅 - 想像力が独特
ひらがな学習には関心を示さなかったものの、自分なりの記号や世界観で張り紙を作る姿に、「学び方が違うだけ」と気づかされました。思いもよらないものの例えや発言、行動には笑ってしまうことが今でもよくあります🤣
◯ ASDへの対応と関わり方
- 言葉ではなく“見える形”で伝える
指示や予定は口頭よりも絵や表、タイムスケジュール表など「視覚的な情報」で示すと理解しやすくなります。時間の違う6種類のカラー砂時計が幼児の時大活躍でした⏳ - こだわりや興味を尊重する
好きなもの(例えばタイピングやバスケ)をどんどん伸ばすことで、自信につながります。苦手より“得意”に目を向けることがカギです。とにかく熱中します。タイピングは親が計画的に仕向けましたがバスケは自分でハマりました🏀 - 安心できる“ルールと予測”を用意する
変化に不安を感じやすいので、日々のルーティンや事前の説明があると落ち着いて行動できます。急な予定変更はできるだけ避け、予告を入れるようにしています。 - 「できた経験」を積ませる
少しずつ「できた」「褒められた」を積み重ねることで、他人との関わりにも前向きになっていきました。自信をつけるのが一番👍
◆ 長男の特性:ADHD(不注意優勢型)
ADHDとは、「注意がそれやすい」「落ち着きがない」「衝動的な行動がある」といった特性が見られる発達障害です。長男はその中でも「不注意優勢型」で、集中力の維持が難しいタイプです。
◯ 主な特性(長男の場合)
- 集中力が続かない
宿題に取り組んでいても途中でぼーっとしてしまう、忘れ物が多い、道具の準備をしてもすぐ他のことに気を取られる、ということがよくありました。 - 時間の感覚があいまい
「あと5分」が守れず、何度も声をかける必要がありました。急かされるとパニックになりやすく、トラブルにつながることも。毎日保育園前で動画を「あとひとつ見たら行く」と永遠に登園できませんでした😂 - 見通しを立てるのが苦手
複数の作業を同時に管理するのが難しく、提出物や行事の準備が間に合わないことがよくありました。今日が何日、曜日も気にできません・・・ - 興味があることには高い集中力
好きなことにはなかなかの集中力を発揮します。その集中の「スイッチ」をどう入れるかがポイントです。親がスイッチを押すことはできません💦思春期前の土台作りが有効でした!!
◯ ADHD(不注意型)への対応と関わり方
- やることを細かく分けて提示
「宿題をする」ではなく、「5分だけ音読」「次は計算プリント」のように小分けにして伝えると取り組みやすくなります。 - リマインダーやスケジュール表を活用
視覚で予定を確認できるように、ToDoリストやタイマー、カレンダーを活用。自分でも見通しが持てるようにしました。 - 声かけは短く・具体的に
抽象的な言葉(「ちゃんとしなさい」など)は伝わりづらいため、「いまはプリントをランドセルに入れてね」と具体的に伝えます。 - “できた”の経験をその場で肯定
うまくいったときはすぐに褒めて「今のやり方よかったね!」とフィードバック。成功体験が次への意欲につながります。
◆ 発達障害の特性は「その子の取扱説明書」
自閉症スペクトラムもADHDも、「その子なりの世界の感じ方や考え方」があるということ。大人がその“取扱説明書”を読み解くように、子どもの言動の裏にある「理由」を知ろうとすることが、何より大切だと感じています。
発達障害の子供の特性は示されますが、個々の特性はみんな違います。一緒に過ごす家族にしか分からない。どう対応するのが良いか手探りで毎日試行錯誤でした。子どもたちの「得意」や「個性」に光を当てながら、彼らが安心して過ごせるような環境をつくっていきたいといつも考えています❤️
→☕️「母だから」全部頑張らなくていい。発達障害兄弟の子育てで見つけた、わたしなりのバランス🥰
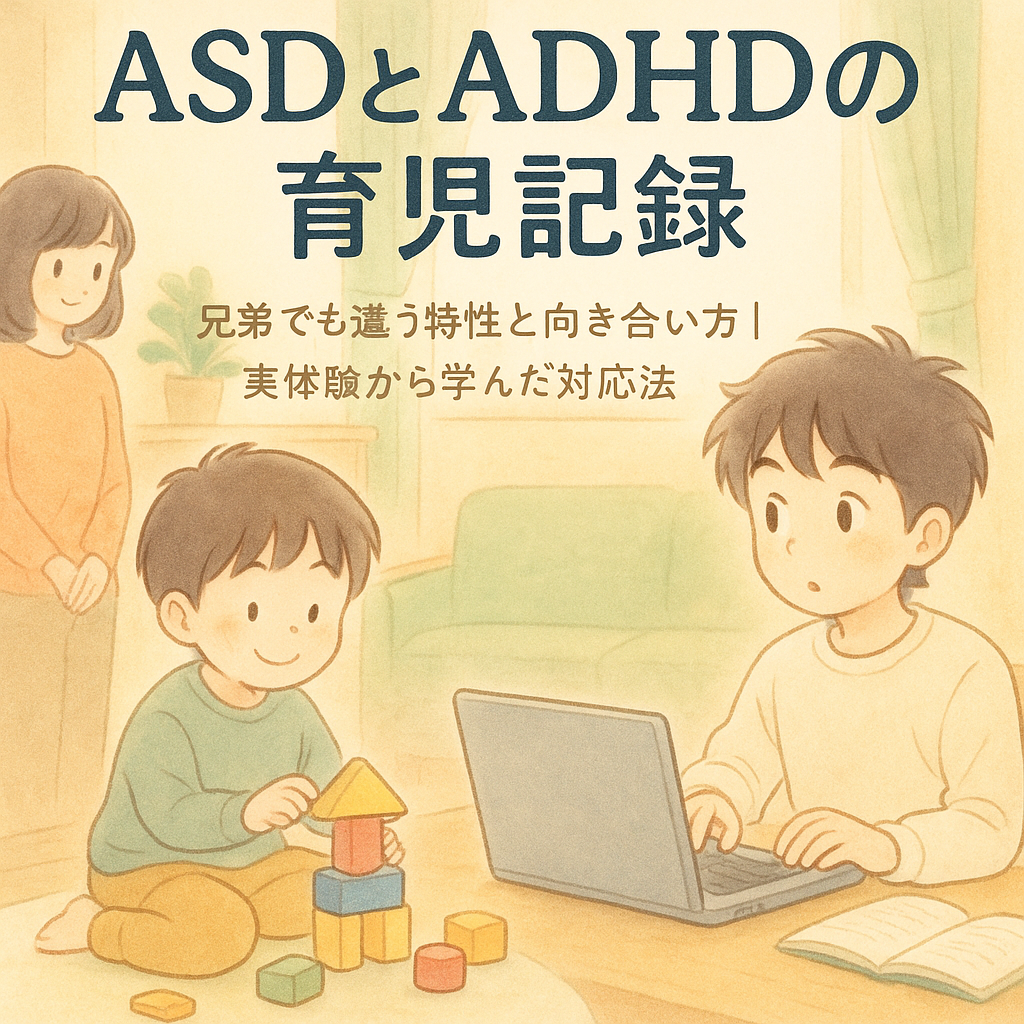



コメント