🏀 保育園から小学校までの成長の軌跡
次男は、保育園時代から「ちょっと変わった子」でした。
常にマイペース。毎日、一人で歌を歌いながら砂場で遊んだり、工作に没頭したり。
周囲と関わることは少なくても、彼なりにとても楽しそうに過ごしていたのです。
そんな次男の後を、自然と何人もの子どもがついて行き、先生からは「みんなのアイドルなんです」と言われるほど。
集合写真ではいつも真ん中、散歩で摘んだ大量のつくしも名前入りで飾られていました。
一方で、私は誇らしさと同時に“違和感”を感じていました。
🏀 取り残されていく、けれど本人は平気
年中〜年長になる頃、周囲の子どもたちが集団での遊びに夢中になるなか、次男は次第に取り残されていきました。
他の子に合わせて遊ぶことが難しく、どんどん「浮いた存在」になっていったのです。
それでも次男は気にせず、一人で楽しそうに遊んでいました。
ある時、特定の女の子から日常的に叩かれたり押されたりするようになり、ようやく「嫌だ」と口にするように。
けれど、うまく言葉で伝えることができず、周囲の大人にも気づかれにくかったのです。
🏀 型にはまらない発達のなかで見えた“光”
自宅では、好奇心旺盛で面白いことが大好き。
玄関の鍵を開けて外へ飛び出し、母親の驚いた顔を見て笑ったり、1ヶ月以上「朝は納豆巻きしか食べない」生活が続いたり……。
年長になってもひらがなを書こうとせず、自作の象形文字のような張り紙を家中に貼り、「これは僕が作った文字だから勉強はいらない」と堂々と話す。
言葉の学習はなかなか進まずとも、運動神経は良くて、3歳で補助輪なしの自転車を乗りこなし、走るのも早かった。
ただ、「これは得意なのかな?」と思っても、当時の次男には“好き”かどうかがわからない。
親が促して「得意そう」に見えても、それは本当に本人の気持ちとは限らないのです。
🏀 自信を育てた“先取り”と環境の工夫
次男はADHDの3歳上の兄の影響で通信教育を始めました。
学習の進め方も、先生が次男の特性を考慮し、苦手分野は丁寧にゆっくり進めてくれました。
また九九などは、2ヶ月前から毎日CDで流すことで自然に覚え、「学校ですごいと言われた」と嬉しそうに話す姿も見られるように。
こうした“先取り”は、「できる!」という経験を積む大きなきっかけになります。
次男は4年生になると、兄が通っていたパソコン教室の体験に参加。
この時のために3年の3学期、頑張ってローマ字を教えました。
タイピング練習にどんどん夢中になっていきます。
ゲーム感覚で上達し、ついには先生や大人にも勝つほどのスピードに。
学校で本格的にパソコン授業が始まったとき、タイピングが得意なことから「人気者」になったのです。
🏀 「本当に好きなこと」に出会えた奇跡
6年生になると、体育のバスケットボール授業で、クラスの人気者Tくんに何度もチームに誘われます。
バスケが得意なTくんと一緒にプレーするため、次男は毎日ドリブル練習に励むようになりました。
次男は140cmの小柄な体格。
一方、Tくんは170cmを超える長身。
体格の差があっても、Tくんと過ごす時間は次男にとって大きな自信になりました。
こうして、
- タイピング
- 算数
- バスケットボール
が“本当に好き”な得意分野として育っていったのです。
🏀 「得意」は“好き”につながったとき、子どもを変える
親が用意した得意は、あくまで「きっかけ」です。
本当に子どもを変えるのは、自分で「好きだ」と思えること。
そして、
それを手にするには、長い時間と積み重ねが必要です。
次男も、たくさんの寄り道と試行錯誤の末に、ようやく自分で得意なことを見つけ、自信をつけていきました。
小学校の時、支援級に在籍しながらも、通常級の中でも堂々と学び、活動できるようになったのは、この「得意」があったからです!
(特性は変わらないのでクラスでは浮いた存在ですが本人が楽しく過ごせているのでまあいいかな、と思っています)☺️💦
→🖼️自閉症スペクトラムとADHD──それぞれの特性と親の対応法🪞

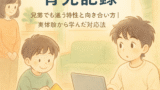
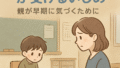

コメント