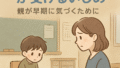──支援級=安心ではなかった。家庭との連携がすべての鍵に
小学校3年生から、次男は支援級での学びを始めました。
でも、支援級に入れたからといって、それだけで「安心」とはなりませんでした。むしろそこからが、本当の意味での“親の出番”だったと、今では強く思っています。
🖐️支援級の先生=専門家ではない現実
支援級に在籍してはじめに気づいたのは、「支援級の先生が必ずしも専門家ではない」という事実です。
ある年は、もともと通常級を担当していた先生が、たまたまその年度の支援級を受け持っただけ。
次の年には異動になるかもしれず、継続的に深い知識や支援技術が引き継がれるとは限りません。
もちろん、支援に熱心な先生もいますし、愛情を持って関わってくれる先生も多いです。
でも、発達障害や学習障害に対する理解度・支援経験には差があります。
だからこそ、子どものことを最もよく知っている親が、支援級という環境をどう活かすか──その視点がとても大切になるのです。
☝️「家庭でできること」と「学校でお願いしたいこと」の明確な仕分け
次男の場合、家では落ち着いて学習できる環境が整っていました。
そのため、計算や漢字の反復練習といった“シンプルで教えやすい内容”は家庭でフォロー。
逆に、言葉の言い回しや、国語の文法、話す力など、“時間をかけてじっくり教えてもらいたい部分”は支援級でお願いしました。
次男は支援級の中では比較的しっかりしている方だったので、先生が1対1や少人数で関わる時間も限られていました。
だからこそ、「ここを中心にお願いします」と親の方からしっかり伝えることが、貴重な支援の時間を有効に使う鍵になりました。
👌教材の持ち込みも柔軟に
支援級では、先生が教材を準備してくれることが多かったのですが、内容やレベルが合わない場合は、こちらから教材を提案することもありました。
市販のプリント教材やネット上のドリルなど、家庭で見つけたものを「こんな形で教えてもらえますか?」と相談。
快く対応してくださる先生が多く、とても助かりました。
🤝面談ノートで情報を一元化
学校との面談は、1学期に1回程度が定期的に設定されていましたが、それ以外にも先生から連絡をいただいたり、こちらからお願いして面談を設けることも。
その際に大切だったのが、「伝えたいことを簡潔にまとめておくこと」。
だらだらと話してしまうと、大事なことが伝わらないまま終わってしまいます。
私は日頃から「支援面談ノート」を1冊作っていて、そこに
- 面談で話す予定のこと
- 日頃気づいたこと
- 支援でお願いしたいポイント
- 面談で決まったこと
を簡単にメモしていました。
そのノートは病院・福祉センター・学校と、どこに行くときも必ず持参。情報を一元化することで、自分の頭の中も整理できましたし、先生にも状況をスムーズに伝えられました。
👋支援を“活かす”には、親の姿勢が不可欠
小学校の6年間は、子どもの土台を育てる時期。
支援級という場をうまく活用できるかどうかは、親の関わり方にかかっていると感じます。
担任の先生に、「うちの子は今こういうところをがんばっていて、ここを特に育てたいと思っているんです」と伝える。
「ここは家でやるので、ここだけは学校でお願いします」と明確に頼む。
そうすることで、先生も「何をしてあげればいいか」が見えやすくなり、限られた時間の中で最大限のサポートが可能になります。
🫶まとめ:支援級=安心ではない。でも、活かせば力になる
支援級に入っただけでは、子どもの成長は約束されません。
でも、親がしっかり子どもの特性を理解し、学校と連携していけば、支援級は「子どもにとって最適な学びの場」になるのだと、私は次男を通して実感しました。
「支援」という言葉に安心しすぎず、でも否定せず、
親として上手に活用していく姿勢が、何より大切なのかもしれません。
→😞支援級の子どもはいじめに遭いやすい?実際に起きた出来事と親の対応(次男)🥲