〜子どもの「食べられない」に隠れた背景〜
🍞 ニュースで知った「パンを喉に詰まらせた事故」
以前、知的障害のあるお子さんが給食のパンを喉に詰まらせて亡くなったというニュースを見ました。
そのとき私は「知的障害があると嚥下機能に異常があるの?」と、とても不思議に思ったのです。
というのも、わが家にも食べ物を飲み込むことに苦手さを抱えている子がいるからです。
🍞 ADHDの長男が食べられないもの
ADHDの長男には、「どうしても食べられないもの」があります。
- 餅(お雑煮やお汁粉もダメ)
- 白玉団子
- イカ(小3のとき夕食で喉に詰まらせて以来)
本人いわく、「飲み込めない」。
噛んで小さくしても、喉の奥で止まってしまう感覚があるそうです。
学童の餅つき大会でも、給食のお汁粉でも、周りが美味しそうに食べている中で一人だけ食べられない。そんな場面を何度も経験しました。
普段の食事では特に問題なく食べられるのに、特定の食材になると途端に「飲み込めない」状態になるのです。
🍞 自閉症の次男は問題なし
一方で、自閉症のある次男にはそうした嚥下の問題はありません。
お餅も団子も魚も、特に詰まらせることなく食べられます。
兄弟で発達障害がありながら心配事はいつも全く被りません。
🍞 小児科で相談してみても…
気になって発達でかかっている小児科の先生に相談してみました。
けれど返ってきた答えは意外とあっさりしたもの。
「飲み込みの異常って感じはないけどね。食べられないなら無理しないでやめておいた方がいいんじゃないですか?」
確かにその通りなのですが、親としては「これって発達障害と関係あるの?」「成長に影響は?」と心配は尽きませんでした。
🍞 発達障害と嚥下機能の関係
調べてみると、発達障害と嚥下機能は必ずしも直接結びついているわけではないそうです。
ただし次のような要因が絡むことがあります。
- 感覚過敏や鈍麻
発達障害のある子どもは、味・匂い・食感などの感覚処理に特徴が出やすいです。
「餅や白玉は喉に貼りつく感覚が気持ち悪い」など、嚥下そのものではなく「感覚の違和感」で飲み込みにくさを感じることがあります。 - 口腔機能や筋力の弱さ
咀嚼や嚥下の動きに必要な舌や頬の筋肉が弱いと、特定の食材を飲み込みにくいことがあります。 - 経験によるトラウマ
過去に喉に詰まらせた経験があると、「また詰まるのでは」という不安から身体が緊張し、実際に飲み込めなくなることもあります。
長男がイカを詰まらせて以来食べられなくなったのも、このケースに近いかもしれません。
🍞 発達障害と他の疾患との関わり
また、わが家の兄弟を見ていると「発達障害がある子は、別の身体的な課題を抱えていることも多い」と感じます。
- 長男:背骨が変形気味で整形外科に通院中
- 次男:低身長で内分泌科に通院中
発達障害そのものが直接原因ではなくても、身体の発達や機能に関わる問題を抱えているケースは少なくないようです。
例えば、注意欠如で姿勢が崩れやすく背骨に負担がかかる子もいますし、ホルモンバランスの異常が発達の特性と並行して見つかることもあります。
🍞 「発達障害=嚥下異常」ではないけれど
結論として、発達障害があるからといって必ず嚥下機能に問題があるわけではないようです。
しかし、発達特性によって「特定の食べ物が飲み込みにくい」「トラウマで避ける」といったケースは確かに存在します。
大事なのは「周りと同じように食べられない=おかしい」と決めつけないこと。正しい状態を把握して必要以上に悩まないこと。
子どもが安心して食べられる食材や調理法を工夫し、どうしても苦手なものは無理せず避けることも立派な対応です。
🍞 親としてできる工夫
- 食材を小さく切る、柔らかく調理する
- 「みんなと同じ」にこだわらず、代替食を準備する
- 苦手な食材を無理に食べさせず、本人の安心感を優先する
- 不安が続く場合は小児科や耳鼻咽喉科で相談してみる 本当に機能障害があり治療が必要なのか、生活の中で詰めないようにさえ気をつけたら良いのか
「食べられないこと」を悩むのではなく、「どうしたら安全に楽しく食べられるか」に視点を切り替えることが大切です。
🍞 まとめ
発達障害と嚥下機能の関係は単純なものではなく、感覚や経験、身体の発達などさまざまな要因が絡み合っているようです。
長男のように「餅や団子がどうしても飲み込めない子」もいれば、次男のように「何でも食べられる子」もいる。
同じ家庭でも、同じ発達障害でも、全く違うのです。
だからこそ、「うちの子はどうかな?」と個別に見てあげることが大切。
そして「食べられないこと」そのものを否定せず、無理のない工夫でサポートしていければ安心だと思います。
→🍚発達障害と食事のむずかしさ
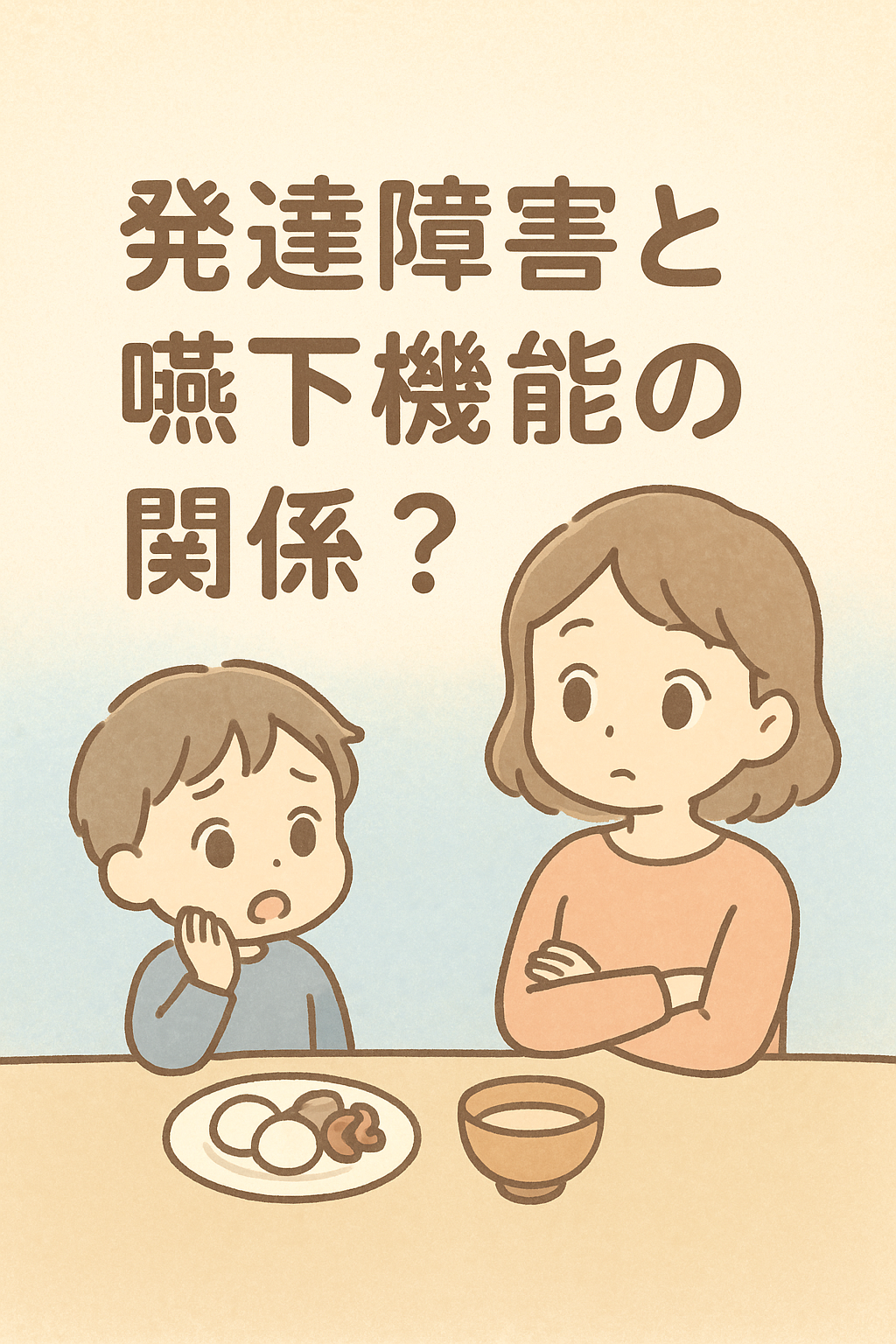
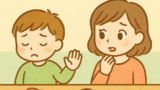

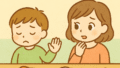
コメント