発達障害のあるお子さんは、特性そのものに加えて、身体の不調や症状を抱えることが少なくありません。
吃音(どもり)、チック、夜尿、頭痛、昼夜逆転、不眠、低身長など、一見「発達」とは無関係に思えるこれらの症状は、実は子どもの心身のストレス反応や神経の働きと深く関係しています。
我が家の長男は吃音・チック・頭痛・夜尿、次男は不眠・低身長にずいぶん悩みました💦
未だ改善していない症状もあり、です。
この記事では、それぞれの症状がなぜ出るのか、どう対応すれば良いのかを具体的に解説します。
吃音(どもり)
■どうして起こるの?
吃音は、「ことばを出す準備が脳の中でうまく調整されない状態」です。
発達障害、とくに自閉スペクトラム症(ASD)やADHDの子では、感情の高ぶりやプレッシャーへの反応として出ることがあります。
■具体的な対処法
- 矯正しない・指摘しない:「ゆっくり話して」などと言わず、安心して話せる環境を作ります。
- 家庭での声かけ:「あなたの話が聞きたいよ」と伝え、内容に集中して聴くことが大切です。
例:「あーあーあー、あのね…」と何度も繰り返す子に「落ち着いて!」と制止してしまうと逆効果になります。
チック(まばたき、肩すくめ、喉鳴らしなど)
■どうして起こるの?
チックは無意識に出る動きで、自律神経が過敏になっている状態を示しています。
発達障害の子はストレスや環境の変化に敏感なため、チックが出やすい傾向があります。
■具体的な対処法
- 環境を整える:静かな空間、急かさない声かけ。
- 疲労・緊張のコントロール:予定を詰めすぎない、好きな活動でリラックス。
例:新学期やテスト期間になるとチックが強くなる子もいます。本人は気づいていないことも多いです。
夜尿(おねしょ)
■どうして起こるの?
夜尿は、「膀胱が発達段階にあること」や「睡眠中のホルモン分泌の遅れ」「ストレス」が影響しています。
ASDの子は刺激への鈍感さ・睡眠障害があることから夜尿が長引く傾向があります。
■具体的な対処法
- 夜尿を責めない:起きたことより、どう過ごすかに目を向ける。
- 水分調整と排尿習慣:夕方以降の水分を減らし、就寝前にトイレへ。
- 夜尿用アラームや紙パンツの活用も検討。
例:「またおねしょしたの⁉︎」ではなく「冷たくなかった?体ふこうね」で信頼関係を保ちます。
頭痛・腹痛
■どうして起こるの?
身体に原因が見つからない頭痛や腹痛は、心理的ストレスが身体症状として出ている場合が多いです。
感覚過敏・緊張の蓄積が関係することも。
■具体的な対処法
- 生活リズムを整える:寝不足や食事の偏りも要因になります。
- 症状日記をつける:何曜日・何時間目・どんな前後関係で出るか把握。
- 学校との連携も重要です。
例:「お腹痛い」で保健室通いが続くとき、時間割の中の苦手科目に注目してみると原因が見えることも。
昼夜逆転・不眠
■どうして起こるの?
発達障害の子は、メラトニン(睡眠ホルモン)の分泌リズムが乱れやすいため、夜眠れず朝起きられないことがあります。
■具体的な対処法
- 朝の光を浴びる:メラトニンのリズムを整えます。
- 寝る前ルーティンを作る:読書や音楽など決まった行動で心を落ち着ける。
- デバイスは夜20時以降オフに。
例:寝る直前までYouTubeを見ていた子に、紙の漫画やストレッチへ切り替えると改善したケースも。
低身長
■どうして起こるの?
ADHDやASDの子の中には、成長ホルモンの分泌リズムが乱れやすいケースがあります。特に睡眠の質が悪い場合、身長の伸びに影響が出ることも。
■具体的な対処法
- 睡眠の質を高める:成長ホルモンは入眠後2〜3時間に多く分泌されます。
- 小児科で相談:低身長が気になる場合、早めに成長ホルモンの検査を受けることも重要です。
例:寝付きが悪く夜中に何度も起きてしまう子が、日中の運動量を増やしたことでぐっすり眠れるようになり、半年で身長が大きく伸びた例もあります。
おわりに:症状は「問題」ではなく「サイン」
これらの症状は、子どもの心や身体が今がんばっているというサインです。
本人に「治す努力」を求めるのではなく、まわりの環境調整や関わり方の工夫が第一歩になります。
「叱らないこと」や「気にしないこと」ではなく、子どもの声なき訴えを読み取ることが、最も必要な支援です。
→🧠発達障害とIQ検査の関係|種類・方法・手順と、IQは上がるのか?

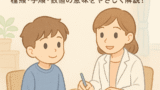
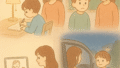
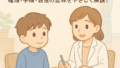
コメント