発達障害の特性をもつ子どもは、どうしても周囲の子よりも理解や行動に時間がかかる場面があります。感情のコントロールも難しいことがあり、特性を知らない子どもたちの目には「変わった子」「おかしい子」と映ってしまうことも。
学校では多様性への理解を育む授業が行われていますが、それでも残念ながら、子ども同士のトラブルや時には教師との摩擦が起きることがあります。今回は、私の次男が小学校で実際に体験した「いじめのような扱い」と、それにどう向き合ったかをお話しします。
■ 支援級の子どもはいじめのターゲットになりやすい?
次男は自閉症スペクトラムの診断を受けており、普段は大人しくて穏やか。ただ、相手の意地悪に気づかないことも多く、本人にとって何が「いじめ」かが判断しにくい面があります。
例えば、小さな嫌がらせや悪意のある言葉でも、次男はスルーしてしまうタイプ。逆に言えば、本人が明確に「つらい」と感じているときには、すでに状況がかなり深刻になっている可能性があります。
■ 担任教師による信じがたい対応
小学校2年生のとき、私は思いもよらない場面に出くわしました。ある日、次男が「工作板が見つからない」と訴えたことから、夕方に教室を訪ねると、教室の後ろ隅に、まるでゴミ置き場のように物が積み上げられ、その中に次男の机が斜めに押し込められていました。
職員室で担任に事情を尋ねると、なんと大声で「何も返事ができない子どもに困ってるんですわ」と怒鳴りながら、次男の“できなさ”を延々と語り始めたのです。周囲に他の先生がいる職員室前で、まるで晒し者のように次男を罵る声が響いていました。
私はその場では冷静に話を聞くふりをしながら、全てをスマフォで録音。そして後日、支援の責任者に相談しましたが、「あの先生はそうなんですわ」と言うばかりで、対応は皆無。同じ学校内で、教師間に上下関係もなく「ヒラ同士ですから」とのことでした。
■ 校長との面談と“その後”
これは異常だと判断し、校長・支援担当・担任の三者面談を申し入れ。録音音声と机の写真、当時の詳細メモを提示すると、校長は驚いた表情で「すぐに対応します」との返答。次男を支援級に移し、今後は生活全般のフォローを行うという提案がなされました。
担任の交代を求めましたが、「それはできない。ご理解ください」と一蹴されました。
また、次男以外にも同様に「担任により不登校になった児童」が2人いたことも分かりました。3人とも発達グレー、支援計画のある子どもたちです。
校長はその子たちも含め、支援級でのサポートを強化することで「この件は納めてほしい」と要望してきました。親として苦しい判断でしたが、次男の今後の学校生活を守ることを優先し、その条件で受け入れることにしました。
■ 発達障害の子どもは「伝えられないことが多い」
発達特性のある子どもは、体調不良や不安の原因をうまく言葉で説明できません。学校での小さなトラブルが積み重なって、ある日突然「もう行けない」と爆発することもあります。
親として大事なのは、
- 学校からの連絡だけでなく、家庭での様子の変化に敏感になること
- 学校で何が起きているか、定期的に確認すること
- 子どもの話に出てくる些細な違和感も大切にすること
この時期(コロナ禍の直後)は学校が休校明けで様子がつかみづらく、次男の不調にも気づきにくい状況でした。もし私が偶然、教室に立ち寄らなければ、もっと深刻な事態になっていたかもしれません。
■ まとめ:支援があるからといって、安心しきらないこと
支援級や特別支援教育の制度があっても、それをどう運用するかは学校・教師次第です。支援級だから安心、ではなく、親として“常に見守り、必要ならば介入する”姿勢が必要です。
また、子ども自身が理不尽な扱いを受けたとき、どうやって助けを求めればいいのかを伝える練習もしておくべきだと感じました。小さな違和感を放置せず、気づいたときにすぐ動く。これが、親として子どもを守るためにできることです。
→💻自閉症のある次男の「本当の得意」を見つけるまで(次男)🏀
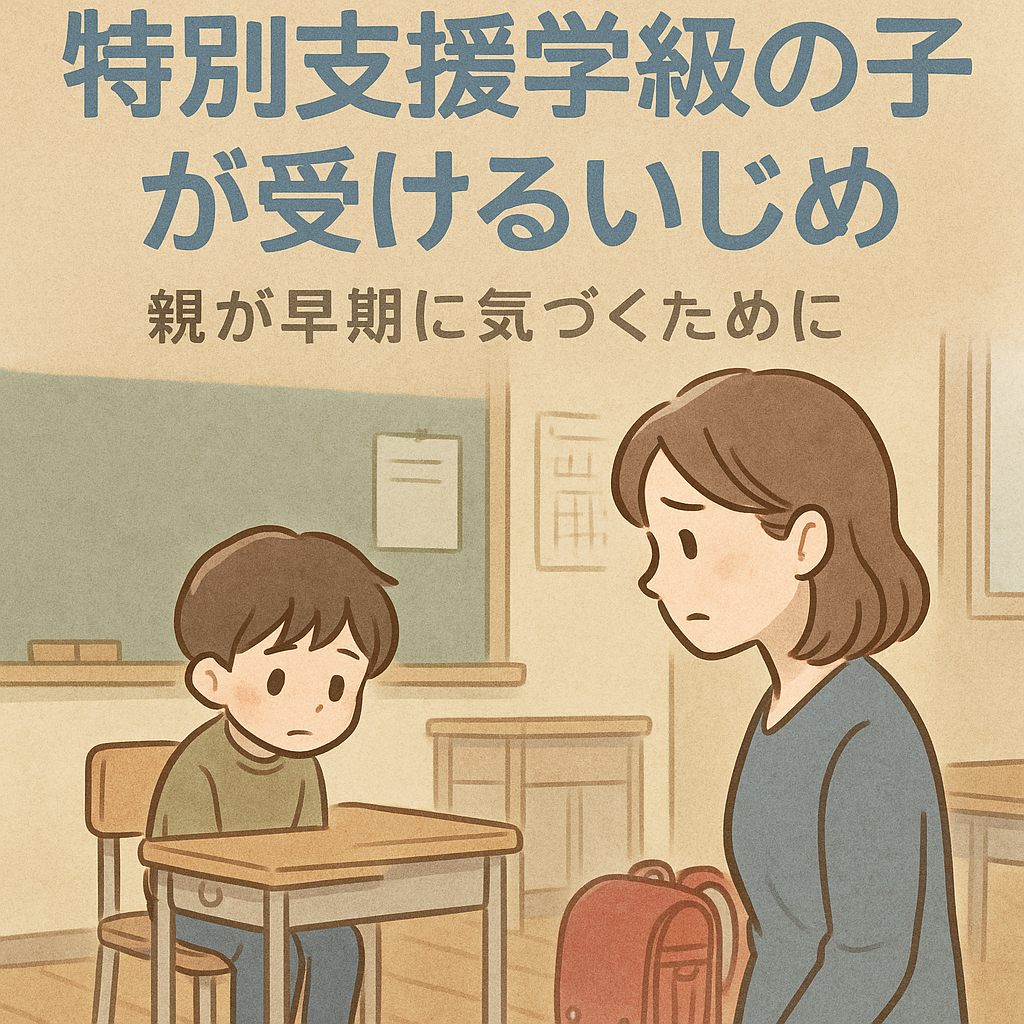
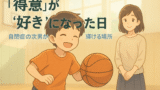


コメント