〜長男の中学1年のつまずきから学んだこと〜
⌛️ 小学校では何とか踏ん張れた長男
小学校時代、長男は色々と困難がありながらも不登校にはならず、何とか通い続けることができました。
しかし中学校1年生になった途端、環境の変化や授業の仕組みの違いから、少しずつつまずき始めます。
⌛️ 中学の授業スタイルと提出物の壁
中学では教科ごとに先生が変わり、提出物も科目ごとに異なります。
長男は黒板の指示をメモすることが苦手で、覚えておくのも難しいタイプ。テスト前には大量の提出物が必要でしたが、1学期は1つも提出できませんでした。
親の私も中学生活の細かい様子は見えず、思春期に入った長男はそっけない態度。助言やチェックをすると、明らかにイライラして距離を置こうとしました。
⌛️ 初めての3者懇談で知った現実
1学期末の3者懇談で、提出物が全く出ていないことを先生から聞かされました。
「家は休める場所にしてあげてください。勉強は学校で全部フォローします」と先生。
正直「そんなことが可能なのか…?」と不安でしたが、1年生だし気楽に構えようと任せてみました。
しかし2学期も同じ結果に。
⌛️ 徐々に出てきた生活リズムの乱れ
朝は起きられない日が増え、食事量も少ない。寒くても薄着で登校し、夜中にゲームをしていることもありました。
「このまま不登校になってしまうのでは」と不安が募り、2学期末の懇談で相談すると、先生は笑顔で「明日来なくなってもおかしくない感じです」と言い、「不登校になったら別室があります」とあっさり。
しかし実際、不登校になった子のほとんどは別室にも来ないとのことでした。
⌛️ 不登校になったときのための準備
私はもしもの時のために行動を開始。
- 不登校経験のある親たちと話す機会を作る
- 放課後デイサービスの見学
- 職場に働き方の調整を相談
準備を進めることで、少し心が軽くなりました。
❤️ 幸運な出会いと変化
幸い長男は不登校にならず、2年生になる頃には態度も少し落ち着き、クラスで気の合う友達もできました。
ただ周囲では「また行かなくなった」「学年が変わったら来なくなった」という話が保護者間で飛び交っていました。
⌛️ 子どもの「困っている」は見えにくい
懇談では「本人が困っていないようなので」と言われましたが、後から思えばすでに困っていたのです。
ただ、自分から助けを求めることができないだけ。友達と楽しく過ごしていても、心の中では困り事を抱えていました。
⌛️ 早めの支援がカギ
長男は2年生1学期から「通級」に通うことに。
週1回、通級の先生が困り事を丁寧に見てくれ、教科の先生にも情報共有してくれました。
「職員室に行って質問する練習」など具体的なサポートもあり、本人にとって大きな安心になりました。
⌛️ 中学の不登校は根が深い
文部科学省のデータによると、中学校の不登校は小学校の約2倍の割合。しかも一度不登校になると再登校が難しいケースが多いのが現実です。
「不登校になったら仕方ない」ではなく、「不登校になる前に予防する」ことが大切です。
❤️ 親ができること
- 子どもの小さな困り事を見逃さない
- 具体的なサポートを学校にお願いする
- 家庭でもしもの時の備えをしておく
親が動くことで、学校側も動きやすくなります。
不登校は「なってから対応」では遅いこともある――それを、長男の経験から強く感じました。
発達の心配のある子供を育てる時、いろいろな知識があればどんどん道がひらけていきます!
→📑発達障害の子どもに学習の自信をつける3つの工夫🔠
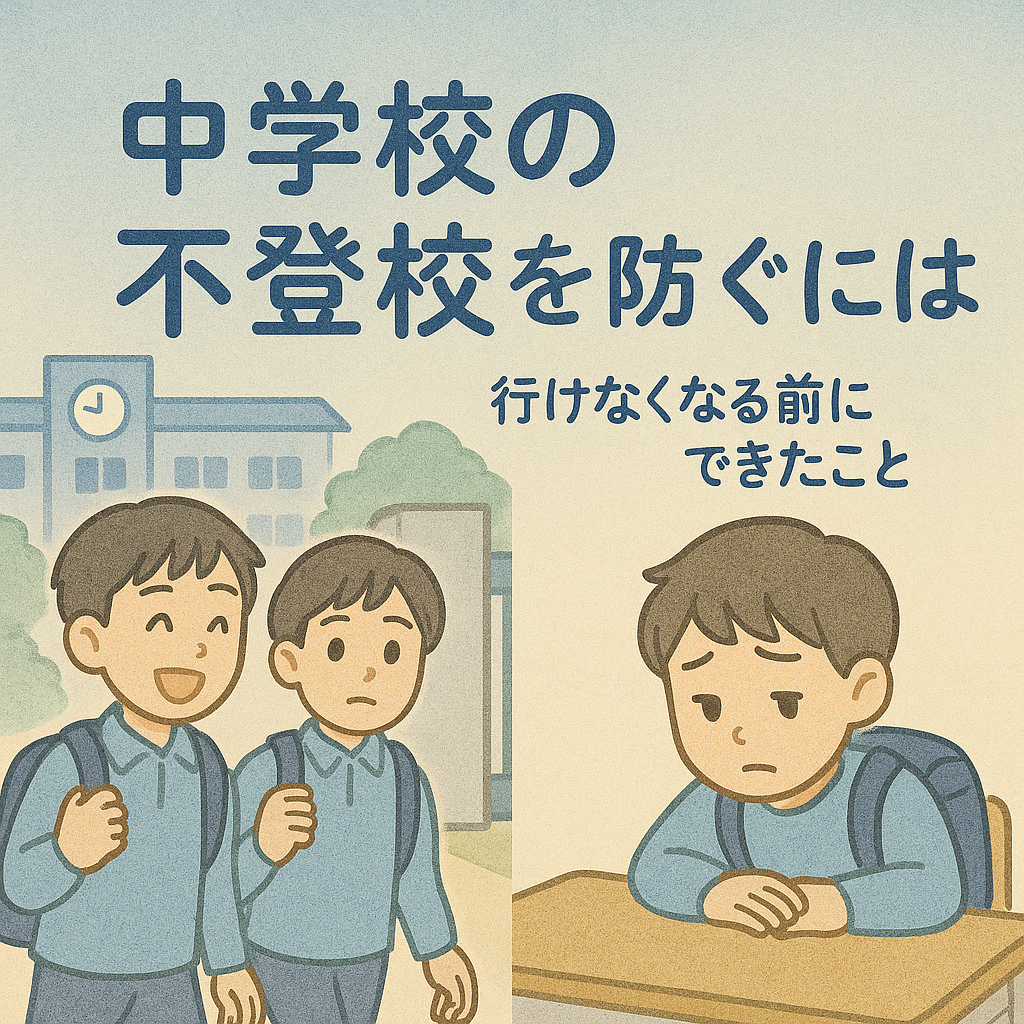
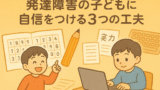

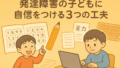
コメント