発達障害のある子どもを育てていると、学校・医療・福祉とのやり取りが多くなります。
「何を誰に聞けばいいのか分からない」「意見を言いすぎて悪目立ちしていないか心配」
そんな不安を抱えながら、なんとか子どもに合った支援を整えていく――それが私の日常でした。
今回は、私自身が実践してきた「情報収集術」と「立ち回りのコツ」を、具体的な体験とともにまとめてみました。
💡 情報収集はどこから?信頼できる人を見つけるには
一番頼りになるのは、「現場の声」。
子どもと日常的に関わってくれている、支援級の先生や通級指導の担当者などが、実は一番実情に詳しかったりします。
とはいえ、先生の数も多く、知識や対応の差も大きいのが現実。
そこで私が心がけてきたのは、「信頼できる人」を早めに見つけること。たとえば:
- 話をしっかり聞いてくれる先生
- 一度相談した内容を覚えていてくれる人
- 自分の知らない制度や選択肢を教えてくれる人
また、一番頼りになるのが、同じく支援を受けているお子さんの保護者。
私はママ友が多い方ではありませんが、一人だけ「ネットワークに強い」ママがいて、支援情報や経験談をよく教えてくれました。
行政や医療の情報はネットにも載っていますが、実際に「今、どこで何ができるのか?」という最新の情報は、やはり現場の声やつながりの中にあります。
💡 あえて“出しゃばらない”関わり方
子どものために一生懸命になればなるほど、つい学校に意見を言いすぎたり、強く要望したくなったりします。私もそうでした。
でも、ある時「どう伝えるか」で結果が変わると気づいたのです。
過度に遠慮する必要はありませんが、「相手の負担を減らすように動く」と、お互いに気持ちよく関われます。
一歩引く姿勢が、結果的に支援につながると感じました。
💡 トラブル時の交渉のコツと心構え
「子どもが授業中にトラブルを起こした」「学校で対応に納得できないことがあった」
そんな時、親としてどう動くべきか悩みますよね。
私が気をつけていたのは、感情的にならずに「状況を整理する」こと。
- 何が起きたか
- どんな背景があったか(家庭での様子や診断内容など)
- こちらの要望は何か(感情ではなく、目的を明確に)
また、単独で動かず、支援センターや福祉の相談員を通すと、冷静に話を進めやすくなります。
先生に話す時に「病院の先生(発達での主治医)にも相談しているんですけど、はっきり伝えた方が良いと言われたんで聞いてもらってもいいですか」と前置きするだけで話しやすくなります☺️
「味方がいる」というだけで、心の余裕も生まれます。
大事なのは、相手を責めないこと。
先生も悩んでいることがあります。子どもを“被害者”や“加害者”として一方的に決めつけず、「どうすればよかったか」を一緒に考えるスタンスを持つようにしました。
💡 情報は「つながり」で活きる
せっかく集めた情報も、活かせなければ意味がありません。
支援計画、学校への引き継ぎ、家庭での記録——それらを「つなげる」ことがとても重要です。
私は、定期的に家庭での様子を簡単に記録しておき、支援会議の際に見せられるようにしていました。
診断書や経過記録もファイルでまとめておき、いつでも相談の場で出せるように準備。
情報は“集めるだけ”では意味がない。“活かせるように整理しておく”ことが、親にできる一つの大事な支援でした。
💡 おわりに
子どもに必要な支援を整えるために、親としてできることはたくさんあります。
でも、全部一人で抱え込まなくていいんです。
信頼できる人に頼ること、うまく関わること、少しずつ経験から学んでいけば大丈夫。
「(言い方は)控えめに。でも話す内容は遠慮しない。」
このバランスを取りながら、これからも、親としてできることを探していきたいと思います☺️
→🏫小学校入学、支援級が良い?通常級が良い?― 親として迷った、あの春の日のこと(次男)🌸
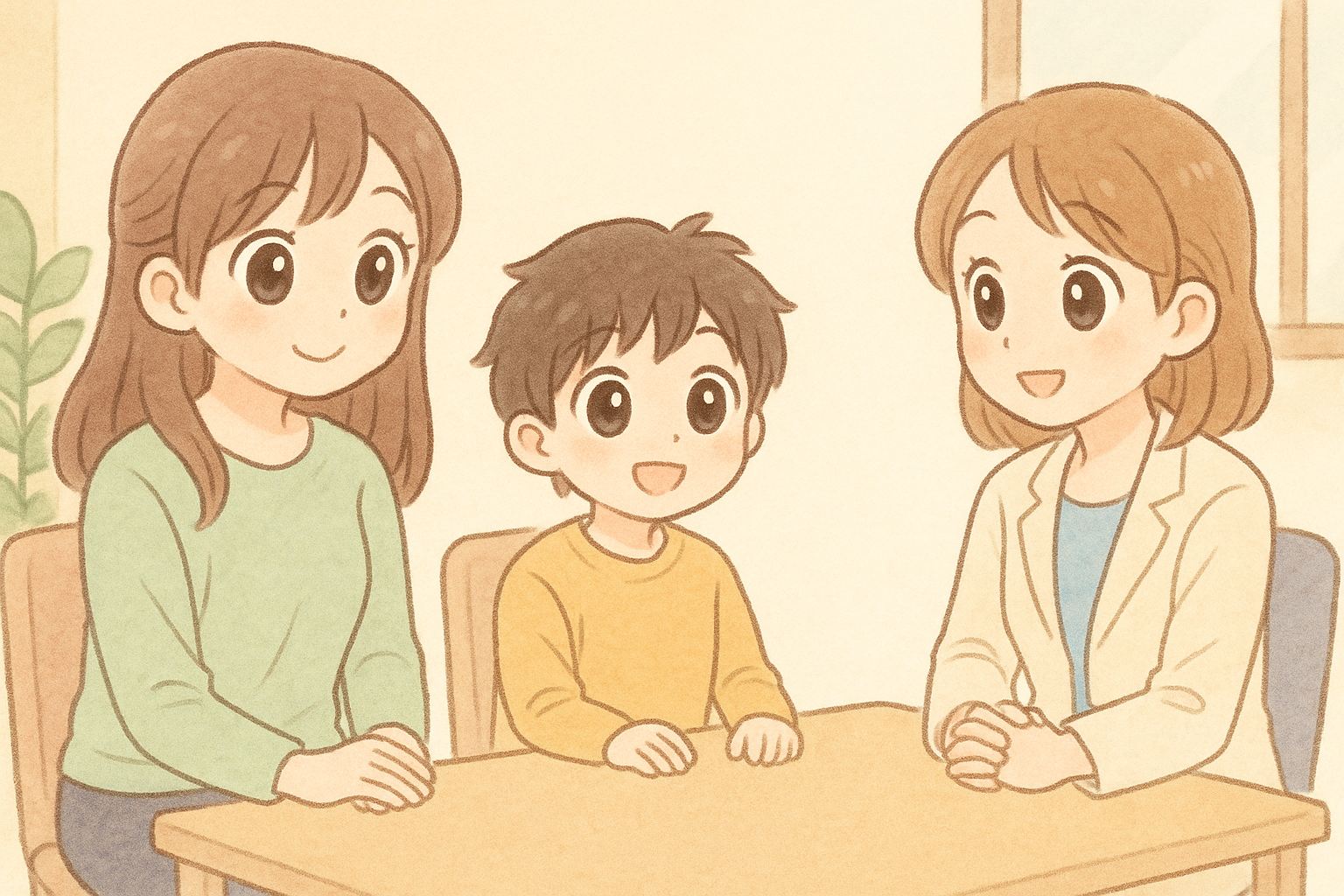



コメント