発達障害の診断を受けた子どもに「薬を使いますか?」と医師に提案されると、多くの保護者は戸惑うと思います。「本当に必要なの?」「副作用は大丈夫?」「飲み続けるの?」――私も、長男が小3の時に服薬を始めたとき、まさにそのような気持ちでした。
今回は、わが家の経験も交えながら、発達障害児の服薬について、わかりやすく説明します。
長男に出た症状と、薬をすすめられた経緯
長男が小学校3年生のとき、担任の先生との関係がうまくいかず、学校に行くのがしんどそうな日が続きました。やがて、チック(まばたきや体のピクつき)や頭痛、吃音(きつご)などが現れ、心身ともに不安定な状態に。
病院で相談した際、医師から「薬を試してみますか?」とすすめられました。処方されたのは「ストラテラ」という薬です。
正直に言うと、そのとき私は「何に効くのか、わからない薬を飲ませていいのだろうか?」と迷いました。医師の説明はこうでした。
- 効果が出るまでに数週間から数か月かかる
- 効く場合もあるし、何も変わらないこともある
- 副作用(食欲減退や眠気など)が出ることもある
- 3か月ほど飲んで様子を見るのが一般的
まるで“試しに飲んでみる”ような印象に驚きましたが、その頃の長男のつらそうな様子に「藁にもすがる気持ち」で、服薬をスタートしました。
ストラテラとは?どういう薬?
ストラテラ(一般名:アトモキセチン)は、ADHD(注意欠如・多動症)の子どもや大人に処方される薬です。中枢神経の働きを調整し、「注意力」や「落ち着き」「集中力」を改善する効果があるとされています。
・依存性はない
・ゆっくり効果が出る(即効性ではない)
・脳内のノルアドレナリンの働きを整える
・朝に1回飲むのが基本(長男の場合は朝夕で処方されました)
・副作用としては、食欲減退、吐き気、眠気などが報告されている
あくまで、「行動を無理やり抑える薬」ではなく、本人の状態が整うことで、生活がしやすくなることを期待する薬というイメージです。
服薬してどうだったか? 我が家の記録
長男はストラテラを飲み始めて3か月、目に見えて「チック」「頭痛」「きつご」は落ち着いてきました。
ただし、同時期に担任の先生が産休で交代し、新しい担任が発達にとても理解がある方でした。長男にとって安心できる環境になったことで、不調が治まったとも考えられます。
つまり、「薬が効いた」とは断言できないのが本音です。
一方で、前から苦手だった「文章を読んで理解すること」が、少しできるようになってきたように感じました。それが成長の結果なのか、薬の影響なのかもわかりませんでしたが、特に副作用もなく、少なくとも害はないようだったため、服薬は継続しました。
効果は実感しづらい。でも「なんとなく穏やか」
ストラテラは即効性がある薬ではないため、「飲んだらすぐ落ち着く」「行動が劇的に変わる」というような効果は、わが家では感じませんでした。
・飲み忘れても特に問題は起きなかった
・飲んでいても特性自体は変わらない
・でも、なんとなく穏やかに過ごせている
そんな曖昧な感じです。
それでも、本人が大きく困っている様子もなく、「薬を飲むことで日常が安定するなら」という気持ちで、今も服薬を続けています。
他にもある発達障害児の服薬と考え方
発達障害の薬には、ストラテラ以外にも以下のようなものがあります(ここではごく簡単に紹介します)。
| 薬名 | 主な対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| コンサータ | ADHD | 即効性があるが、依存性や副作用に注意が必要。 |
| インチュニブ | ADHD(落ち着きのない子) | 血圧を下げる作用があり、眠気が出やすい。 |
| リスパダール | ASDや不安の強い子 | 強い不安や攻撃的な行動への対応に用いられる。 |
| エビリファイ | ASD、不安、うつ傾向など | 不安の緩和や情緒の安定を目的に使われることも。 |
※薬は医師の診断と判断によって処方されるもので、安易に比較したり「この薬が良い」とは言い切れません。
⭐️次男は一度コンサータを試しましたが特に変化がなかったため1ヶ月くらいで中止になりました。
まとめ:服薬は「万能な解決策」ではないけれど…
発達障害の子どもに薬を使うことは、とてもセンシティブな選択です。
私自身、薬に抵抗がなかったわけではありません。むしろ、「薬を使う=何かが間違っているような気がする」と感じました。一方、この症状が薬で劇的に改善するのでは、との期待もありました💦
実際、あの頃私の心に余裕があったら薬は試さなかったかもしれません。しかし、試してみてこわい物ではないことがわかりました。服薬に踏み切ったことで、少しでも長男の負担が減ったのならよかったと思っています。
効果が見えにくくても、悪くはなっていない。飲まなかった時と比べることはできませんが、「試してみた経験」が私自身の安心につながったのも事実です。
服薬は「治す」ためではなく、「今を生きやすくするための補助」だと思っています。医師との相談や環境とのバランスを取りながら、子どもと一緒に探っていく。柔軟に考えて良いと思います!
→💡発達障害の子育て中に気づいた「もしかして私も?」|大人の発達障害に気づいた親の体験と診断の流れ


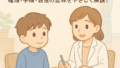
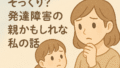
コメント