🌻 通級・カウンセリングを学校で活用する方法と働きかけ方
発達障害やグレーゾーンの子どもたちにとって、「安心して気持ちや困りごとを話せる場」は、学習支援と同じくらい大切です。
我が家の長男も、中学時代は「通級」、高専進学後は「校内カウンセリング」を活用しながら、安定した生活リズムや学びを取り戻していきました。
この記事では、通級・カウンセリングなどの相談の場を学校でどう活用するか、具体的な手順や働きかけ方、対象になる子どもたちの条件などについて、体験を交えながら解説します。
🌻 通級指導教室とは?(小中学校)
通級とは
通常学級に在籍しながら、週に数時間だけ特別な支援を受けるための指導教室です。
対象は、発達障害(ADHD・ASD・LDなど)の診断がある子だけでなく、診断がなくても支援が必要と認められた子も含まれます。
どんな子が対象?
- 集団行動が苦手
- 学習の遅れやつまずきがある
- コミュニケーションに不安がある
- 感情のコントロールが難しい など
発達に不安があれば、すでに担任の先生には相談済みだと思います。
先生の方から勧めてくれれば良いのですが、通級について理解していない先生も多いです😅
通級でできること
- 苦手な教科の個別支援
- 人間関係や不安への対応
- 「困ったときにどうすればいいか」の練習
- 自己理解を深める支援 など
我が家の場合は、1対1で定期的に何でも聞いてくれる先生。思春期以降、全く母に相談できない→頼れる大人がいない状態、だった。なのですぐに先生と仲良くなって何でも相談していたようです。すごく助かりました!
その中で苦手・困り事を聞き出してくれて、会話の練習やロールプレイングもしてくれていたようです☺️
利用したいときは誰に言えばいい?
最初の相談先は、『担任の先生または学校の特別支援コーディネーター(支援担当)』です。
学校によっては、校長や教頭が窓口になる場合もありますが、まずは担任に「通級を検討したいのですが」と伝えると、教育委員会や校内の支援会議につないでもらえます。
実際の手順(参考:長男の場合)
- 担任へ相談(中一の時 長男の場合、担任の先生から声をかけてくれました)
- 校内支援会議 → 通級の見学
- 教育委員会への申請・判定会議
- 利用開始(授業中・放課後)
- 長男の場合は『授業中に抜けるとクラスの他の子にわかってしまうので放課後にしてほしい』と本人からの申し出があり通級の先生が水曜日の放課後の1時間を確保してくれました。2年生時は週1回、3年生になったら月に2回になりました。(希望者が多かったため)
🌻 高校・高専・大学では?(通級の代わりになる支援)
高校以降は、通級制度が基本的にありません。
代わりに、多くの学校では校内の「相談室」や「カウンセリング」の制度が整備されています。
高専でのカウンセリング活用(実体験)
長男が高専に入学した際、校内に常駐の『心理士(カウンセラー)』の先生がいることを説明会で知り、入学後すぐに面談を予約しました。
カウンセラーの先生は初対面から優しく、長男はすぐに心を開いたようです。初めての学校、寮生活に期待と同じくらい不安があったと思います。定期的な対話を通して、自分の状態を振り返る機会になり、精神的な安定や自己理解が深まっていったようです。
対象になるのは?
- 発達障害の診断がある子
- 人間関係・学業・寮生活に不安がある子
- 精神的に不安定な様子が見られる子
診断の有無に関係なく、「困り感」があれば利用可能です。
カウンセリングを受けたいときは誰に言えばいい?
- 担任の先生
- 保健室の先生(養護教諭)
- 教務・学生課(高専や大学の場合)
- スクールカウンセラーの先生がいる場合は直接予約も可能
長男の場合は、説明会の場で「支援希望」と伝えたことで、入学後すぐ心理士との面談予約が入りました。
🌻 学校の支援を上手に活用するコツ
親から「困っていること」を具体的に伝える
支援を受けるには、「何に困っていて、どうしてほしいか」を明確に伝えることが大切です。
例)
・授業中に集中が続かない
・忘れ物が多く、トラブルが起きやすい
・本人が学校で安心して過ごせない
本人の意思も尊重する
特に中高生以降は、本人の希望がないと支援に消極的になることもあります。
まずは「話だけでも聞いてみない?」など、心理的ハードルを下げた声かけが効果的です。
相談先は複数ある
担任だけでなく、養護教諭・学年主任・スクールカウンセラー・支援コーディネーターなど、学校にはいくつかの相談窓口があります。
「この先生なら話しやすそう」という相手を見つけるのも大切です。
🌻 まとめ:通級もカウンセリングも「ひとりじゃない」と感じられる場所
通級指導もカウンセリングも、「困り感を抱えた子どもがひとりにならない」ための支援です。
子どもにとってはもちろん、親にとっても
「いつでも相談できる場所がある」
「見守ってくれる人がいる」
というのは、想像以上の安心につながります。
進学や進級など、環境が大きく変わるときこそ、「相談できる場を確保すること」をひとつの優先項目として考えてみてください。
支援を受けることで、子どもたちは「誰かが自分を理解してくれる」という安心感を持ち、また一歩、自立に向かって成長していけるのだと思います。
我が家の場合は小学校時は通級の先生は近隣の小学校から定期的に来てくれる先生だったため、特に希望はしませんでした。
毎日見てくれている担任の先生や学年主任の先生が身近にいてくれたので、わざわざ他の学校の先生と定期的に面談しても・・・、と判断したのです。
しかし、中学生になって担任の先生と保護者の距離が遠くなり、何でも親に筒抜けの生活でなくなった時、頼る場所として本当に安心できる存在でした。保護者にも。もちろん、長男にも。
中学校時代につかんだチャンスの中で一番大きいのが通級の先生との出会いだったと思います!
進学してすぐに同じような支援が受けられてとても安心しています!知らなくて支援をスルーしたらもったいないです。今後の成長に大きく関わることと思います!
→📡発達障害の子を支えるために|親としての情報収集術と立ち回りのコツ💡
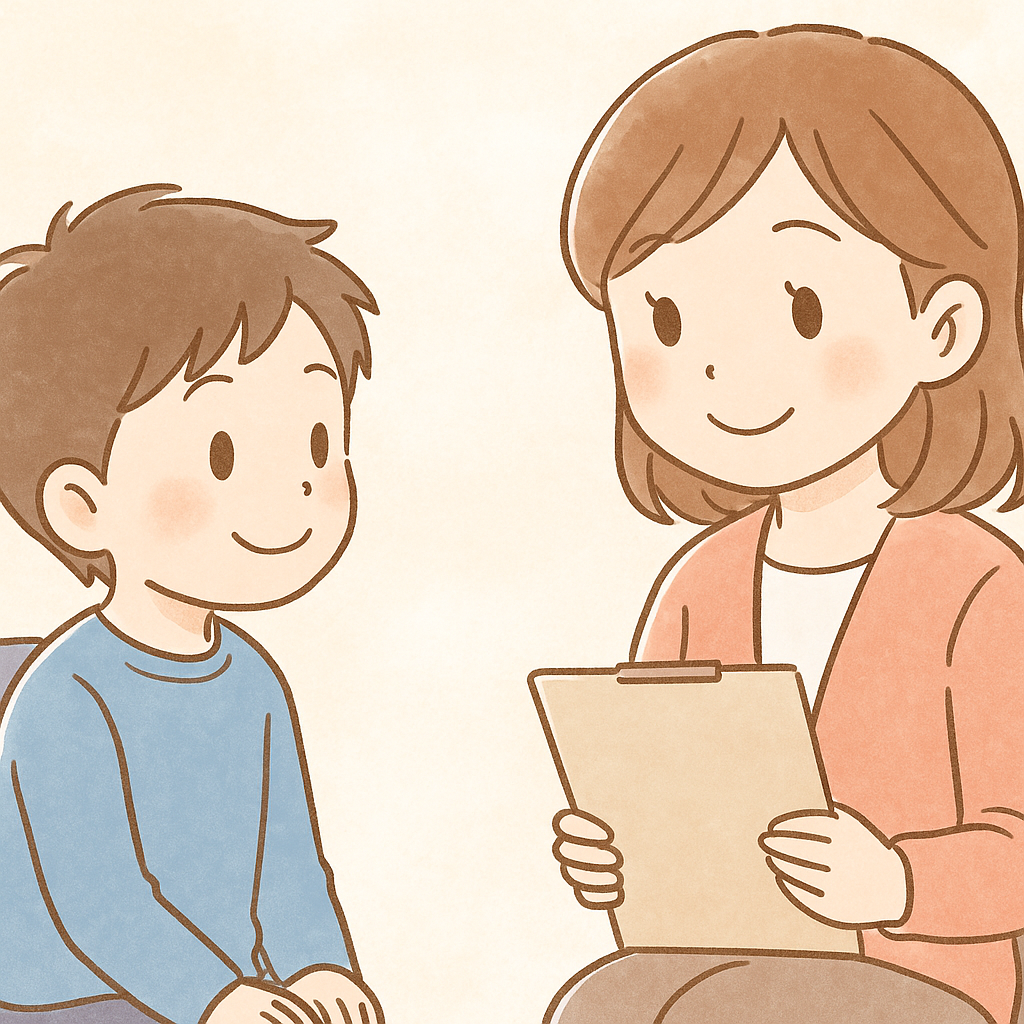
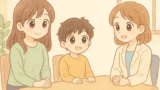

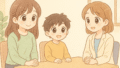
コメント