――心理士の言葉に救われた私の体験
発達障害のある子どもを育てていると、
「このまま手を出しすぎたら過保護なのでは?」
「自分でできるようにさせなきゃ」
と悩む場面が多くあります。
私自身も、長男・次男の成長とともに同じように迷ってきました。
🍀 小学校高学年になると訪れる「手を出す・出さない」の葛藤
わが家の次男は、自閉症の特性があり、小学校高学年になっても幼児のように甘えてくる子でした。
一方の長男はADHDで、忘れ物やスケジュール管理がまったくできません。
そんな二人を育てながら、私はよくこう思いました。
「これ以上手を出したら、甘やかしすぎなのかな?」
「もっと本人に任せた方がいいのかな?」
特に小学校高学年に上がる頃は、子どもも少しずつ自立を求められる時期。
親として「どこまで手を出すか」の線引きにとても悩みました。
🗣 心理士さんの言葉で気持ちが軽くなった
そんなときに出会った心理士さんの言葉が、今も私の子育ての軸になっています。
「いつかは子どもの方が鬱陶しがって、親から離れていきます。
だから親子の総意の間は、思う存分甘やかしてあげてください。」
この言葉を聞いた瞬間、心の中の迷いがすっと軽くなりました。
「甘やかしていいんだ」――そう思えるようになったのです。
👦 わが家の「甘やかし方」
もちろん、すべてを親がやってあげるのではなく、
忘れ物やスケジュール管理は「少しずつ自分でできるように」と促してきました。
でも、どうしてもできないことは「しょうがない」と思い、必要なら手を出しました。
- 甘えてくる次男は、とことん可愛がる
- 長男は中学生になり「放っておいてほしい」と言うことが増えたが、時々は甘えてくる
- そんなときは「よしよし」と受け止める
子どもが甘えたいときに甘えさせる。
それがわが家の「甘やかし方」です。
🏫 中学生になっても続くサポート
中1の次男は、今も変わらず甘えてきます。
学校の生活サイクルや提出物の管理も、私が先回りして把握しています。
「過保護だな」と思うこともあるけれど、私はこれでいいと思っています。
親が見守り、手をかける時期は中学卒業まで。
高校に入れば、きっと本人の意思が強くなり、親の出番は自然と減っていくでしょう。
🚪 長男の「親離れ」と「親への甘え」
長男が中3のとき、高専の寮に入りたいと言い出しました。
「もしかしたら、親が甘やかしてきたのが鬱陶しくなったのかな」と思いましたが…
実際には、寮に入ってからも頻繁に帰省したがり、長期休みには友達と同じくらい家にもいました。
「距離を持ちつつも甘えられる関係」が続いているのです。
🌸 今、思うこと
あのとき心理士さんに「甘やかしていい」と肯定してもらえたことで、私は迷いなく子どもを可愛がれました。
結果として、子どもとの関係は良好で、今も親子で安心できる関係を築けています。
発達障害のある子どもは「幼い」と見られることも多く、親はどうしても過保護にならないようにと悩みがちです。
でも、親子が心地よく感じる範囲であれば、甘やかしてもいい。
それが私の経験から伝えたいことです。
✅ まとめ
- 発達障害の子育てでは「過保護では?」と迷う場面が多い
- 心理士の「甘やかしていい」という言葉で救われた
- 子どもの「甘えたい気持ち」を尊重して関わる
- 甘やかすことが結果的に良い親子関係を作ることもある
親子の形は家庭ごとに違います。
でも「わが家のやり方でいい」と思えたとき、子育てはぐっと楽になります。
→

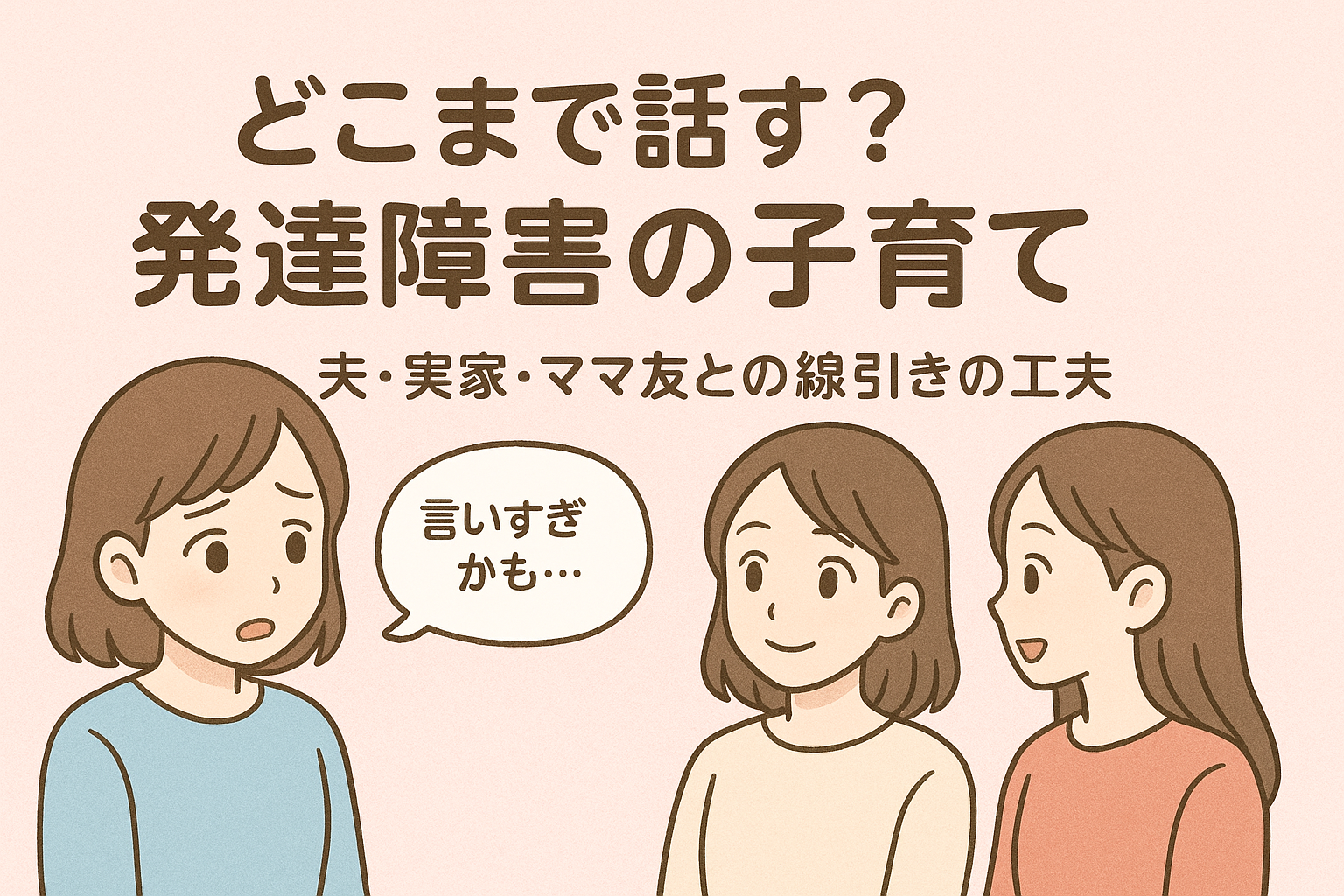

コメント