子どもの発達に悩みを抱えるようになってから、私は気づいたことがあります。
「小学生で発達に課題を持つ子は、男の子が圧倒的に多い」ということ。
そして、兄弟がいる場合は、まったく違うタイプの特性を持っていることも珍しくありません。
兄は音に敏感で、こだわりが強いタイプ。
一方、弟は落ち着きがなく、思ったことをすぐ口にしてしまうタイプ、とか──。
我が家も例にもれず、まったく違う「困りごと」を持った子どもたちと向き合っています。
🌷 家庭によって違う「育て方」の選択
発達に悩むママたちと話すと、本当にそれぞれの家庭で選んでいる方針が違うことに驚かされます。
ある家庭は、
「普通に育てたい。できるだけ周囲に合わせて生きていけるようにさせたい」
という方針で、小学校の通常級で何とかやっていくことを大事にされています。
またある家庭は、
「早いうちに診断を受けて、支援の制度を使い倒した方が、結果的にラクだし子どもにとっても良い」
という考えで、支援学級や医療機関に積極的にアクセスしています。
一方で、育児と仕事に追われる中で
「方針を持つ余裕もなく、目の前のことをこなすだけになっている」
という声もあります。
旦那さんとの方針の違いで悩むママも少なくありません。
夫は「診断なんて大げさ」「もっと厳しく育てればいい」と言う。
妻は「もっと環境を整えてあげたい」と思う──。
こんなふうに、家庭内ですら意見が一致せず、モヤモヤを抱えたまま子育てしている方も多いのではないでしょうか。
🌷 ママ友はたくさんいなくてもいい。でも…
私は、正直に言えば「ママ友がたくさん欲しい」と思ったことはありません。
むしろ、興味本位でいろいろ聞いてくる人、勝手に話を広める人が怖くて距離をとってきました。
でも、それでもやっぱり『「本音を言える誰か」とつながれることは大きい』と、最近感じています。
それは、同じように発達特性のある子を育てているママ。
できれば、我が家と似たような方針や価値観を持っている家庭の人とつながれたら、本当に心強い。
たとえば、支援学級に在籍しているママで、上のお子さんがすでに中学生だったりすると、
「こんなふうに進学することもできるよ」
「学校ではこういう配慮を受けられたよ」
と、具体的な経験からくれる言葉に説得力があります。
🌷 情報と安心感を得る「ママ友」という存在
ママ友って、何となく付き合ってるイメージを持たれがちですが、私はこう思っています。
「お互いに必要な情報を持っているからこそ仲良くなる」
そこから少しずつ、気が合えば、自然と「本当の友達」になっていく。
最初から無理に仲良くしようとするのではなく、
「条件が合うこと」=子どもの状況や通っている学校が似ていることが大事。
たとえば、うちの子と同じ小学校・同じ支援級に通っている子のママとなら、
「この先生は理解があるよ」「こういうプリントが配られるよ」
と、自分だけじゃ集めきれない情報を得られる。
そして、学校や医療機関とは違う、「親」という立場で、同じ悩みや迷いを持つ者同士でしか交わせない言葉があります。
他のママに話したらびっくりされることも平気で話せる!とか・・
🌷 家族とも、先生や医者とも違う「伝え合える相手」
家族は心強い存在。でも、すべての思いや不安を同じように受け止めてくれるとは限りません。
先生や医師は専門家として的確なアドバイスをくれますが、それも「仕事」の範囲です。
だからこそ、利害関係がなく、ただ「同じ立場の親」として話せる誰かがいること。
それが、思った以上に支えになることがあります。
たとえば、夜中にふと「うちの子、これで大丈夫なんだろうか」と不安になったとき、
「うちもそうだったよ」「その時期あるよ」と言ってもらえるだけで、
心が少しラクになったりするんです。
🌷 おわりに:つながりは“数”じゃない、“質”だと思う
ママ友はたくさんいなくていい。
でも、似たような方向を向いて、似たような悩みを持つ人と、少しだけつながれること。
それが、子育てにおいてものすごく大きな意味を持つと感じています。
今すでに、周りに信頼できるママがいれば、ぜひそのご縁を大事にしてください。
もし「一人もいない…」という方は、無理に探さなくても大丈夫。
小学校生活、思うように過ごしていたらそのうち出会うことがあると思います。
同じように悩んでいる人は、必ずいます!
→🌎夫婦で子どもの発達を支えるということ──方針が違っても、すれ違わないためにできること🧭
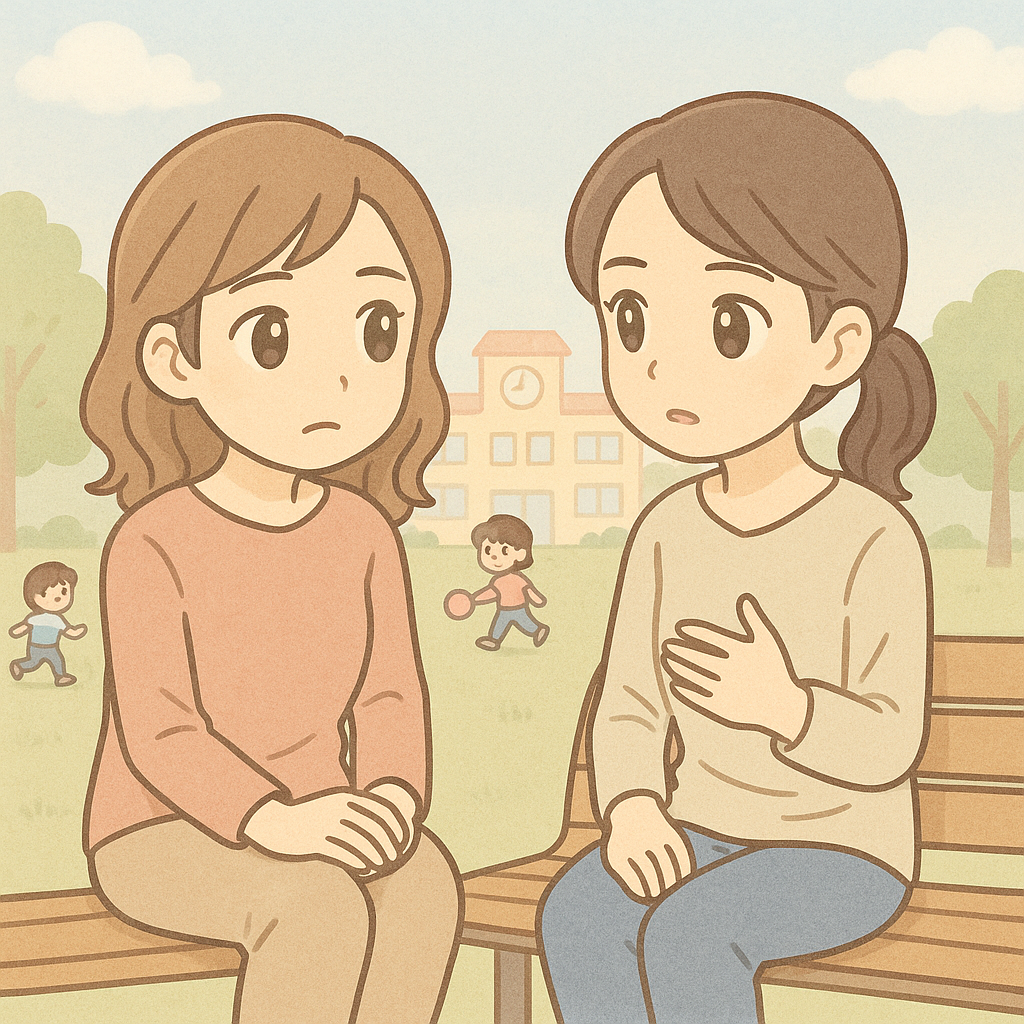
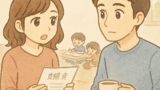
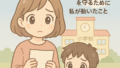

コメント