1. 保育園時代の次男 ― 「多動」と「こだわり」のあいだで
今でこそ、次男は「大人しい子」という印象を持たれることが多いのですが、実は保育園時代はまったく逆でした。
- 集団活動の輪から離れ、一人で別のことに没頭
- 他のクラスの友達のところへ勝手に遊びに行く
- 朝の会が始まっても、平気で違う遊びを続ける
一言でいえば「落ち着きがない子」。けれども、本人は悪気があるわけではなく、“そのとき興味のあること”に真っ直ぐなだけだったのです。
そんな次男の様子から、保育園では年少クラスの頃から福祉関係の面談が定期的に行われるようになり、年長の秋には「就学相談」を受けるよう勧められました。
2. 支援級?通常級?就学相談の結果に戸惑う
就学相談では、面談・行動観察などが行われました。保育園側からは「支援級が合っていると思います」との見立てがありましたが――
結果、役所から出た判定は「通常級で可。どうしても支援級を希望されるなら相談ください。」とのことでした。
私は親として、内心とても迷っていました。
- 支援級に入れば、手厚く見てもらえるけど学習が遅れてしまうのでは…
- 通常級に行けば、周りについていけずに困るのでは…
でも、何が正解かわからないまま、判定に従って通常級に進学することにしました。
3. 「伝わっている」と思ったのに、伝わっていなかった
小学校入学前、「保育園の先生が小学校にきっと事情を伝えてくれている」と思っていました。
でも、実際に担任の先生に確認すると…
「特に何も聞いていません」
との返答。
おそらく「通常級入学=特別な支援は必要ない」という認識になり、情報が共有されなかったのだと思います。
支援が必要な子のことほど、“ちゃんと伝わっているだろう”と思い込まないことが大切だと痛感しました。
4. 通常級に入った次男のその後
入学後の次男は、静かで真面目に見えるタイプになっていきました。
でも実際は、
- 授業中に先生の話を聞き逃す
- 自分から質問ができない
- 書くスピードが遅く、ノートが真っ白のまま
というように、「静かに遅れていく子」になってしまったのです。
困っているけれど、助けを求められない。
できないことがあるけれど、誰も気づいていない。
親の目から見て多分そんな状態だろうな、との様子が見られました。低学年のうちは家で学習を見られるけど、学年が上がったらついていけるかなあ・・そんな不安の中の毎日でした。通常級では担任の先生に本人の様子を詳しく聞くことが困難です。生徒はクラスに30人。先生は1人。『うちの子と注意して見守ってください』とはとてもお願いできません。
1年生の面談時の担任の先生からは『特に目立っていないので大丈夫だと思いますよ。テストも普通に受けられているし。』と具体的な困り感やお友達との様子は尋ねても『大丈夫だと思いますよ。いつも一人でいるわけではないみたいだし・・』と。あまり安心できないような『大丈夫』でした。
もしこの先生が上手に面談相手をされる方だったら、面談の当日に次男を気付けてみてくれているかも知れません。私を心配して安心させるように、
『お母さん大丈夫ですよ。今朝も次男くんが困った様子できょろきょろしていたから声をかけたんです。そうしたら「鉛筆を削ってなくて書けない」と言うことができました。だから鉛筆削りの場所を教えて使っていいよ、と声をかけたんです。これからも様子をよくみてこちらから声をかけますね。聞いたら困っていることをいうことができる力はありますよ。』
なんて、エピソードを交えて説明されたら『この先生は次男のことをしっかりみていてくれる。学校でのことはお任せして先生に定期的に様子を聞いたら大丈夫。』と誤解してしまいます。
次男は2年生の時にトラブルがあり学校からの促しで、2年の間はお試し、3年生から正式に支援級に入ることになりました。
支援級のクラスは生徒6人に対して先生1人。(多くても生徒は8人までだそうです)
そして毎日保護者と先生で連絡ノートのやりとりを行なってくれました。先生からは提出物や持ち物、次男に主体的に準備させるにはどうするか、私からは次男の家での困り事、朝の準備が自分でできないので表にして貼っていること。幼児期から不眠があり昨晩あまり寝ていないこと等。毎日タイムリーに伝えられました。
6年生の卒業時、支援級に入れて本当によかった、と思いました。
5. もし、あの春に戻るなら…6年後の今、親として思うこと
今、もしあの入学前の春に戻って支援級か通常級かを選ぶことができたなら――
私は「支援級在籍からスタート」を選びます。
理由はこうです。
- 支援級にいたからといって、学習が遅れるとは限らない 特に小学低学年の学習は量も少なく支援級の時間にできなかったことは家庭学習でカバーできたな、と思いました。
- むしろ「安心できる環境」だからこそ、学びに集中できることがある
- 小学校の“最初のつまずき”を減らせば、その後の伸びにつながる
- 学年が上がると通常級から支援級に移ることで本人がストレスを感じたり、周りからの目が気になったりします。支援級で過ごすなら早い段階が良い
そして、何よりも大切なのは
「本人が安心して過ごせるかどうか」。
支援級か通常級かではなく、『今この子に合っている環境かどうか』を軸に考えることが大切だと、今ならはっきり思います。
支援級所属で様子を見ながら、少しずつ通常級で過ごす時間を作ってもらえたら。支援級の先生、通常級の先生を頼れる環境は良いと思います。
そして通常級に入り、ついていけないなあと思ったら担任の先生や支援担当の先生にすぐに相談するのが良いと思います。
支援級に入る事が必要か(または、できるか)は分かりませんが通級やその他の支援の提案があるかも知れません。
6. 結論:「選んだ道」を正解にするには、情報と連携が鍵
支援級か、通常級か――
たとえどちらを選んでも、親としてできることは「選んだ道を正解にしていく」こと。
そのために、こんなことが大切だと感じています。
- 就学相談だけで終わらせず、「学校に直接伝える」姿勢を持つ
- 支援が必要なら、入学してからでも相談・導入できることを知っておく
- 迷ったら、「安心できるほう」を選ぶ
進路に正解はありません。けれど、子どもに寄り添い、必要なときに必要な支援を届けることは、どんな道でも可能です。いつ、どこにどんな相談を持っていけば子供にとっての良い環境が作れるか。
わが家も長男・次男の成長を見守ってきました。長男の時より情報を得た次男の時の方が上手く立ち回れていたと思います!
→✏️小3で支援級に転籍、その後に見えた「親の立ち回り」の重要性(次男)📔


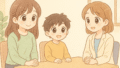

コメント