◆はじめに:「叱り方のコツ」って、どこまで本当に使えるの?
発達障害の子どもとの関わり方について、病院や専門機関でよく聞くアドバイスがあります。
- 怒るのではなく、具体的に伝える
- 大きな声は出さず、静かに・短く
- できたときにすぐ褒める
- 「ダメ」は禁止で終わらず、代わりの行動を教える
- 感情を落ち着ける時間と場所をつくる
——うん、分かる。確かにそうなんですよね。
でも、正直に言えば、
それ、もう分かってるし。
なるべく毎日意識してますけど!?
というのが本音でした。
それでも、うまくいかないことがある。
それは、「教科書通り」では回らないのが現実だからです。
◆わが家の場合:長男は「まず否定」から入るタイプ
うちの長男は、いわゆる“天の邪鬼(あまのじゃく)”。
私の声かけや指示に対して、まず否定から入る癖があります。
「そろそろお風呂入ったら?」
→「今入ると寒いし」
「先に宿題終わらせておいた方がいいよ」
→「いや、後でもできるし」
もちろん、その口調は荒くないし、一見すると“普通の会話”のよう。
でも積もっていくと、親としてはどんどん注意が増えていきます。
「〜しなさい」
「〜した方がいいよ」
「〜はまだ?」
そんなふうに“命令口調”と受け取られる声かけが続くと、長男はますます反抗的になってしまいます。
◆長男への対応:呼び方・口調を変えてみた
そこで私が取り入れたのが、「赤ちゃん返り風の声かけ」です。
長男が高学年にさしかかる頃、
それまで呼び捨てにしていたのを 「〇〇ちゃん」と柔らかく呼ぶようにしてみました(もちろん家の中だけです)。
さらに、注意の仕方も一工夫。
- 「早く寝なさい」→「ねね、まだかー」
- 「目を擦らない!」→「めめ擦らないよ〜」
語尾を伸ばしたり、語彙を幼児語っぽく変えたりして、
反発心を引き起こさない空気を作るようにしました。
本人も「はあ?」と苦笑いしながら、
ふと動き出すことが多くなっていきました。
◆次男の場合:ふざけ倒してナンボ
次男は逆に、素直だけどおっとりマイペースなタイプ。
特性が強く、小学生になっても中身は幼児。“子どもらしい子ども”です。
そんな次男に対しては、「冗談を交えたノリ」が効果的。
◆たとえば…
- 朝、学校の準備をしないとき
→「早くしないとお母さん、〇〇のベッドにゲーして死ぬでー!」 - トイレを促したいとき
→「うんこには勝ったか?うんこに負ける子はうちの子じゃないでー!」
これが、わが家の朝の定番声かけ「うんこに勝ったか?」です💦
子どもはニヤッとして動き始める。
こちらも笑って過ごせる。
叱ることも命令することもない、自然な切り替えのスイッチになっています。
◆家ルールでいい。自分の子にハマる方法が一番
「母親なのに、注意のたびにこんな声かけ…」
「人に聞かせられないくらい、幼稚な会話してるかも」
そんなふうに思ったこともあります。
でも、これが今のわが家のスタイル。
- 本に書かれている「正解」よりも、
- 病院で言われた「理想」よりも、
- 目の前の我が子に合っているかどうかが大事。
真面目に伝えると反抗してしまう子
→ 笑いでゆるく伝える
注意が続くと受け入れなくなる子
→ ふざけた言い方でスッと促す
この“パターン”をいくつかストックしておけば、
注意も日常会話の中で自然にできるし、親のストレスも減っていきます。
◆おわりに:我が子にしか通じない“魔法の声かけ”を探そう
発達障害の子どもにとって、叱られること・注意されることは自己肯定感に直結します。
だからこそ、
「叱らない」「怒鳴らない」は大切だけれど、『どう伝えるか』の工夫がとても重要。
- その子に合った言い方
- その子に合ったタイミング
- その子に合った空気づくり
それらは本にも書いてないし、専門家にも分かりません。
でも、毎日一緒にいる親だからこそ気づけることがある。
それが、「わが家ルール」の強みです。
これからもわが家では、
「うんこに勝ったか?」と言いながら、
子どもとの距離を笑いで縮めていきたいと思います。
→⭐️発達障害の子ども達の将来が不安な私が今思うこと☺️



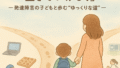
コメント