―学習障害、とは学習するにあったての困難な要因の特性だと勝手に思い込んでいました💦本当の意味は、 私が思っていた“できなさ”とは違っていた・・・子供の特性を関わるにあったって知っておきたい知識です!
◆ 学習障害だと思っていたあの頃
次男が幼児の頃、「そろそろひらがなを教えたい」と思っても、机についてノートを開くことすら難しい状態でした。
じっと座って先生の話を聞くのも苦手で、保育園の集団生活でも落ち着かない様子が目立ちました。
一方、長男はというと、小学3年生頃から宿題や家庭学習の時間になると集中が続かず、30分で終わるはずの課題が毎日1時間以上かかってしまうことがほとんど。
「これはきっと学習障害だ…」と、不安になり日記にそう記したこともあります。
けれど、あとから改めて調べてみると――どうやら私が思っていた“できなさ”は、学習障害とは少し違うようでした。
◆ そもそも「学習障害(LD)」とは?
学習障害(LD:Learning Disabilities)は、
知的発達に遅れはないにもかかわらず、「読む」「書く」「計算する」など特定の分野の習得や使用が極端に苦手な状態を指します。
文部科学省による定義では、
「基本的には全般的な知的発達に遅れはないものの、特定の能力(読み書き・計算など)の習得と使用に困難がある状態」とされています。
つまり、勉強全体が苦手というわけではなく、「ある特定の学習領域」だけが極端に難しいというのが、学習障害の特徴です。
◆ ADHDや自閉スペクトラム症と混同しやすい
学習障害は、ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)と重なっていることが多く、見分けるのが難しい場合もあります。
たとえば、
- じっと座っていられない
- 指示が聞けない
- 宿題に集中できない
こういった特徴はADHDの可能性もあり、必ずしも「学習障害」によるものとは限りません。
私の子どもたちのように、「学習の場面で困ることが多い」=「学習障害」だと思っていたのは、集中力や衝動性など別の特性の影響だった可能性が高いと、今になって思います。
◆ 学習障害の種類
学習障害は、大きく以下のように分類されます。
- 読字障害(ディスレクシア)
文字がうまく読めない/読めるけど非常に時間がかかる
→ 文章の意味が理解できないのではなく、文字そのものの読み取りが困難 - 書字表出障害(ディスグラフィア)
文字を書こうとすると反転したり、順序がぐちゃぐちゃになる
→ 思っていることを文章にするのが非常に苦手 - 算数障害(ディスカリキュリア)
数の概念や計算の順序、量の大小などが理解しづらい
→ 見た目には問題なさそうでも、数の意味が頭に入らない
◆ 「LD=勉強ができない」ではない
「学習障害」と聞くと、「勉強がまったくできない」というイメージを持たれるかもしれませんが、実際にはそうではありません。
学習障害は、特定の分野以外ではむしろ得意なことがあったり、知的には高い力を持っている子どもも多いです。
たとえば、
- 音読ができないけど、口頭での説明は完璧
- 漢字が書けないけど、図や図形の把握は得意
- 計算が苦手でも、理科の実験や観察は大好き
こうした「アンバランスさ」がある場合には、専門機関での評価を検討すると良いかもしれません。
◆ 正確な理解のためには「専門的なアセスメント」を
「学習障害かな?」と思った時、保護者が判断するのはとても難しいものです。
学校や発達支援センター、心理相談室などでWISCなどの知能検査や読み書きの検査を受けると、特性の傾向が見えてきます。
私のように「じっと座っていられない=学習障害」と思ってしまうのは、本質的なLDの理解とズレていることが多いです。
◆ 大事なのは「学習スタイルの工夫」
仮に学習障害があったとしても、適切な支援と環境の工夫で学びの可能性を伸ばすことは十分可能です。
たとえば:
- 音読が苦手な子には、音声教材や読んでもらう方法を
- 書字が困難なら、キーボード入力や口述筆記を
- 数に困難があるなら、視覚的な補助を取り入れて
「どの子も、学びたい気持ちは持っている」
そう信じて、その子に合った方法を一緒に探していくことが大切です。
◆ 最後に:学習障害を正しく知ることから始めよう
私がかつて抱いた「うちの子、学習障害かも?」という不安。
それは、学習障害の正しい理解を持っていなかったことが原因でした。
今の私は、「困っていること」の背景に何があるのかを少しずつ見極め、その子に合った工夫と支援を見つけることが何より大切だと感じています。
発達の心配のある子供を育てる時、いろいろな知識があればどんどん道がひらけていきます!
→🏫小学校の不登校 ― 発達障害を持つ我が家の兄弟と「登校」の壁😟
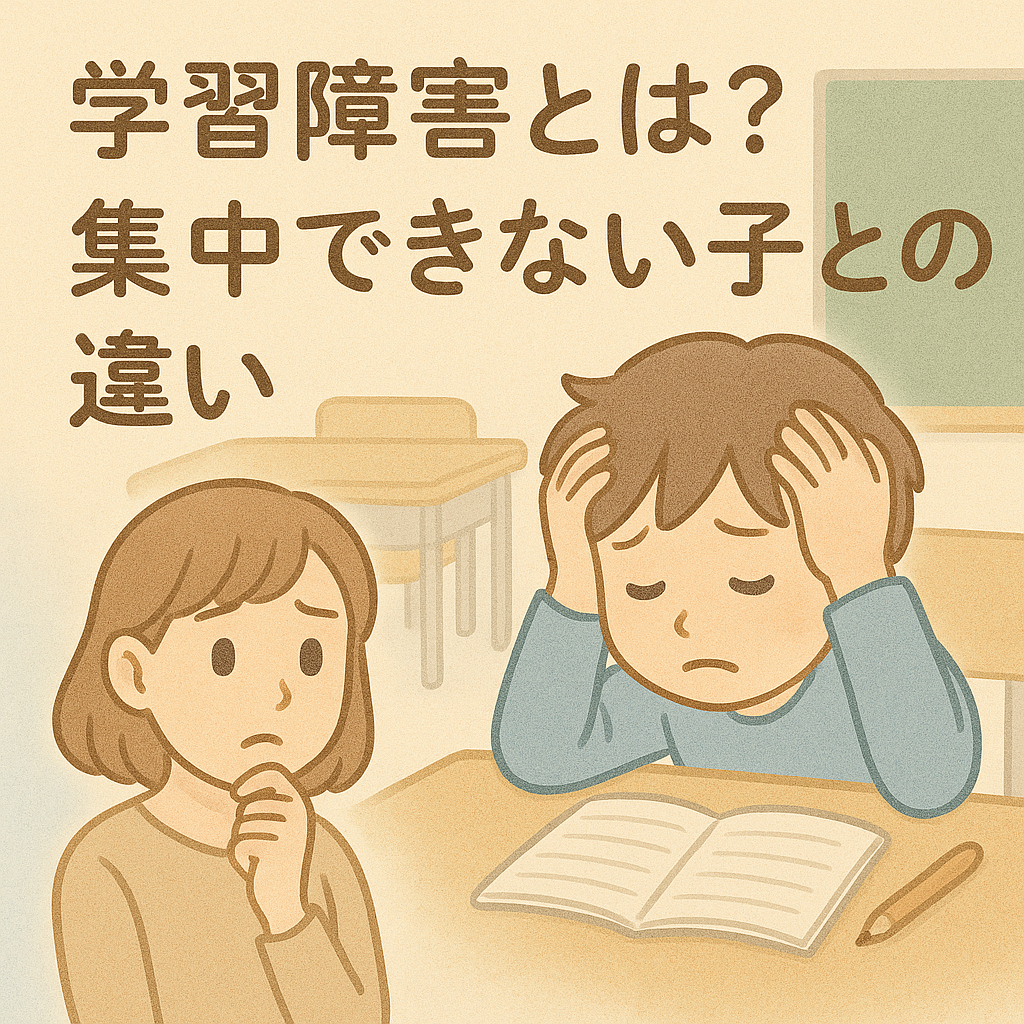
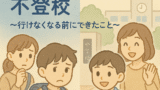
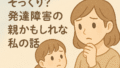

コメント